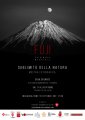Nikon Z7でミラーレスデビュー。D800Eからの乗り替え2ヶ月レビュー(写真は後で)
富士山写真家 オイです。
超久しぶりにブログ発信をします。
今回、思い切ってマウント変更して撮影機材を一新したのでレビューすることにしました。
撮影機材ってなかなか簡単に買えないものなので、実際に使ってみた人のレビューがあると有り難いものですよね。
自分自身も、いわゆる”レフ機”から”ミラーレス”へ初めて移行するにあたっては、かなり使い勝手が変わるんじゃないかなど不安があったので、記録として残しておきたいと思いました。
今回は主にニコン「Z7」の内容となるので、同時発売のZ6や、後継のZ7II、Z6IIをお使いの方にも大いに参考になると思います。
私は2012年4月に発売されたニコン「D800E」を夏に購入してからは、一貫してこのカメラを使い続けていました。
当時、同じフルサイズのD700を使っていましたが、乗り換えたときの描写の進化(精細さとダイナミックレンジ)には感動しました。
あれから8年以上、中古で買い足しながらなんと計5台のD800Eを手にすることになります(常用2台体制)。
実は5台目(5代目)のD800Eを買ったのは最近でした。
それが中古で買ったものの、広角レンズでの描写に甘さが見られ、マウント部の歪み等があると考えられました。
もう古いカメラを中古で買い続けるのは限界かと感じた瞬間でした。
また、以前から愛用していた大三元の70-200mm/F2.8(VR II)レンズを、誤って落下させてしまったことも影響しています。
ニコンの修理に出して戻ってきたのですが、ピントがズレた状態のままで、再調整してもらっても改善せずでした。
メーカーのちゃんとした修理でもダメということは、諦めろと?
また描写においても、ショックの影響か以前より甘くなっているように感じられ、
やはり衝撃を与えてしまった機材は修理しても本来の性能には戻らないのかもしれないと感じてしまったのです。
なお、最も使用頻度の高かった大三元の24-70mm/F2.8レンズも幾度となく修理送りとなっています。
(最後の修理でかなり良くなって戻ってきた感じがしています。)
長く撮影活動をしていれば機材へのダメージはある程度は仕方なく、そろそろ一新かな、というところでした。
手持ちの機材への不満が(自分のせいで)溜まりに溜まった結果の乗り替えとなったのです。
新しい機材は気を引き締めて注意深く使用しようと誓いました。
今回、機材を新調したのは2020年11月です。
カメラはニコンの『Z7』を選びました。
実は、次に狙っていた機材はFUJIFILMの中判ミラーレス・GFXシリーズ(GFX 50S、GFX 50Rなど)でした。
どこまでも最高の描写を追い求めたくなりますね。
ただこれまでいわゆる”大三元”を愛用してきた身からすると、フジ中判のレンズのラインナップ的には使い勝手がかなり心配でした。
F2.8の明るさが欲しければ単焦点しかないし、ズーム域も狭くて頻繁にレンズ交換が必要になってしまう。
また、被写体として花モノ(前景のお花など+富士山)を撮る場合は被写界深度の浅さが裏目に出ます。
お値段もかなりなので諦めていましたが、そこに飛び込んで来たのがニコンZシリーズの評判でした。
噂によれば、Zのレンズはスゲェということでした。
どうもニコンさんはミラーレス開発にあたって過去のFマウントを思い切って捨て、大口径のZマウントを新しく作った。
その大口径を生かしたレンズがあまりにも素晴らしい、というのです。
中判カメラに求めるのはやはり描写(解像力)がメインなので、レンズがそれだけ素晴らしいなら中判に太刀打ちできるのではないか、と考えました。
当然、ずっとニコン使いなので操作性を考えればニコンで乗り換えるのが一番シンプルです。
また、今までと同様のスペックの”大三元”がちょうど出揃ったタイミングとなり、これまでの使い勝手をそのままミラーレスに移行することができます。
ということで、決めました。
また購入当初は、後継機の『Z7II』が発表されたところでしたが、その仕様がZ7とほとんど変わらないようなものだったので、ならば値下がりしたZ7のほうが狙い目だろう、と考えました。
なおニコンのミラーレスにはもうひとつ『Z6』がありましたが、私の撮影は風景がメインで解像感を重視しており、既存機材のD800E(3630万画素)より画素数が下がるというのは考えられませんでした。
よって4575万画素のZ7をチョイスし、その画質に期待することにしました。
今回購入した機材はカメラボディ1台=Z7とレンズ2本=Z24-70mm/F2.8、Z70-200mm/F2.8。
レンズに関しては、本当は大三元を全て揃えるのが理想でしたが、あまりにも高額なので、これまで使用頻度が高かった標準と望遠の2本をチョイスです。この2本があれば8~9割の撮影に対応できるイメージです。
今回の機材投資に際しては、2021年版カレンダーの売上や、皆様から頂いた多大な寄付を元手として充てさせていただきました。
コロナ禍の中、この鞍替えの決断に踏み切れたのは間違いなく支援して下さった皆様のお陰です。
なお”ミラーレスデビュー”と書いたのですが、2011年にニコンD700を買うまではPanasonicの「GH1」を使っていましたので、実はミラーレスは初めてではないのです。
嘘付きましたごめんなさい。
それでは本題のレビューに入ります。
(いったん先行公開ということで、画像なしのレビューをお送りします。後で写真や画像を追加します。)
今回の機材購入は2020年11月で、この記事を書いているのが2021年1月です。
ちょうど丸2ヶ月くらい使用したことになります。
この2ヶ月間は、新しい機材に慣れるため、また使用感を掴むために、普段より積極的に撮影に出ました。
やはり新しい機材を持つと気持ちも上がり、精力的になれる部分もあります。
長年やっていると、マンネリ解消に機材を替えるというのも大事になってくるかもしれません。
そして最も大事なポイントですが、あくまで乗り換え前に使っていた機材との比較がメインであることと、使用者(=私=オイ)の主観であるということです。
またこれも大前提ですが、私は富士山専門の写真家ですので、屋外の風景や富士山をメインに撮影することが前提となります。
そしてスチル(静止画)オンリーで、動画やタイムラプスは撮影していません。
情報を整理すると、旧機材がFマウント(一眼レフ機)で
・ニコン D800E
・AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED(旧型)
・AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II(旧型 VR II)
新機材がZマウント(ミラーレス機)で
・ニコン Z7(初代)
・NIKKOR Z 24-70mm f/2.8S
・NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
です。
なおD800Eの後にニコンからは後継機としてい一眼レフのD810、D850が発売されていますがそちらは使ったことがありません。
性能・機能的に大きな差がなく、あえて新製品を買わずともD800Eで満足していたためです。
というわけでここからは、新しい『Z』の機材を使ってみて気付いた点を書いていきます。
間違いもあるかもしれませんが、気付いたら教えて下さいね!
それではいきます。
最初に2ヶ月使ってみた結論を言ったほうが良いでしょう。
結論を一言で言うなら、「代え難い魅力もあるけど、強烈なインパクトはなく、改善点は多々ある」といったところでしょうか。厳し目に言うと。
D700からD800Eに替えたときほどの感動はないです。
あのときはセンサーの進化が凄かったんです。
また値段が高額なことを考えるとコスパはやや微妙で、”どうしても”という点がなければ中古のレフ機を買った方が圧倒的にコスパは良さそう。
製品ライナップの現状から言うとレンズは素晴らしいがボディはまだまだという世間の声が非常に正しい気がしています。
現在まだD800Eを1台は手元に残していますが、すぐにこれを処分することはないでしょう。
確かに良い点はあるものの、レフ機のほうが良い点もいくつかあり、ある意味当然ながら、「完全に代替される」ということにはならないと思われます。
ここからは項目ごとに詳しく掘り下げていきます。
乗り換えを検討している人の参考になれば幸いです。
ボディはめちゃくちゃ軽くて小さくなりました。やはりこれぞミラーレス。
フルサイズカメラなのにオモチャのようなサイズ感です。ミラー機構が無いことでメチャ薄くなりました。
それでいてグリップ部分はしっかりしているので片手で持っても割と安心です。心配していましたがホールド感は大丈夫。
軽量化の恩恵としては、持ち運びがラクというところですが、それは色々な運搬に関わってきます。
ザックに入れて登山する場合などが最も恩恵がありそうですが、それ以外にも手に持ったまま歩く場合や、三脚に固定したまま持ち運ぶ場合などにも軽いほうが助かります。
三脚に固定時は、雲台の締め付けが弱くて動いてしまうようなことも少なくなるし、持ち運びや操作で疲れにくいということは、より丁寧な取り扱いや、丁寧な撮影に繋がります。
「体力温存」は意外と重要な写真撮影のテーマです。
コンパクト化のデメリットはあまりないのですが、強いて言えば薄くてレンズ交換が少しだけしづらい感覚があります。
あとは前後に幅のある大型の雲台においては、ボディが薄すぎるためレンズが雲台に干渉してしまいます。
定番のハスキー雲台でZ24-70を装着するとかなりギリギリの状態に。
あとは後述しますが、各ボタンが小さくなったため、手が大きめの人は操作しづらいかなという印象です。
セレクター+OKボタンの部分がかなり小さく、「OKボタン」は爪で押すような感覚に近いです。
まだ余白はあるのでもう少し大きくして欲しいところ。
手の小さい女性くらいでちょうどいいサイズ感に思えます。
男性の手だと、かなり繊細な操作が必要。
また、D800系と比べると、P/M/A/S等のモード変更がダイヤル式に変わり、左手での操作になります。
右手だけでモード変更ができなくなってしまいました。
その分、右手だけで拡大・縮小やメニュー表示ができるようになりましたが、好みがあるでしょうね。
レフ機の「ボタンを押しながらダイヤルを回す」タイプの操作は、一見分かりづらいものの実はかなり使いやすくて良かったのですが。
ボタンについては2つのファンクションキーを含め、色々とカスタムできるので自分好みにカスタマイズすると便利になると思います。
ただ、割り当てられない機能があったり、メニューを呼び出した後に選択する動作が必要だったりと、全てを思い通りにすることはできず妙にストレスが溜まります。
操作の手数を極限まで少なくするのが良いデザインだと思います。
またかなり個人的な感想ですが、シャッターの近くにあるISOボタンと露出補正ボタンを間違えやすく、また露出補正ボタンは良く使う割には押さえにくい位置にあるように思えます。
その割に、画面表示を切り替えるDISPボタンが妙に離れていて押しづらいです。
基本的には悪くないとは思いますが、まだ改善の余地はありそうです。
そしてボタンイルミネーション(ボタンが光る)はなしです。
D850に搭載されている機能です。
指で覚えてしまえばいいのですが、せっかくなら光って分かりやすい方が良いですよね。
バッテリーの問題があるのかもしれません。
Fマウント大三元とZマウント大三元での比較になりますが。
標準域のZ24-70/2.8は少し軽く、小さくなりましたが、驚くほど小さいわけではありません。
また既存の機材が旧型の24-70だったので、フィルター径が77mm→82mmにアップしました。
既存システムではレンズキャップやフィルターも共通で使い回せて便利でしたが、まあここは我慢しよう。
望遠域のZ70-200/2.8は、正直言ってあまりFマウントとサイズが変わりません。
こちらもFマウントでは旧型のVR IIを使っていました。
重さはいくらか軽くなっているようですが、大きさはほぼ変わらずコンパクト化にならずです。
ただ描写は素晴らしい!(後述)
広角域のZ14-24はまだZマウント版は手にしていませんが、知人のものを触らせてもらったところ、神レンズと言われていたFマウント版よりかなり小型軽量化していました。
大口径マウントは広角レンズには恩恵が大きいようですね。
最初は気付いていなかったのですが、Z7のベース感度はISO64。(公式な仕様ではベース感度という言葉は使われないですが。)
ベース感度が低いと使い勝手は悪いですが、ダイナミックレンジが広くなる等、低感度での画質に恩恵があるようです。
ニコンD700のベース感度は200。D800Eは100でした。
D810から64を採用しているとのこと。
Z6はベース感度100なので羨ましい。
D800EではISO100と200でほとんど画質に差がないように感じられ、ISO200をほぼ常用していました。
それが今回ベース感度が64となり、ISO200を使うと少しノイジーな感じ。
細かくみればある程度ノイズ感が見て取れます。
今までは気軽にISO200でしたが、Z7では可能な限り感度を下げて撮るようになりました。
高画素化の影響が明らかにありそうで、あとはノイズ処理の程度や鑑賞サイズを合わせた場合に厳密にどう違うかも検証したいですね。
もしかすると同じ条件に揃えると大差がないかもしれません。
手持ちの場合は感度を下げるとブレやすくなりますが、それに関しては手ブレ補正が打ち消してくれそうです。
厳密な検証をしていないので感覚値ですが、話に聞く通り高感度性能はD800Eからほとんど変わらない印象です。
少し改善しているのかもしれませんが、気付かないレベルです。
センサーの高感度性能は、D800シリーズが登場してからほぼ頭打ちに近い状態です。
ソニーのカメラはセンサー性能が頭一つ抜けているとのことで、羨ましく見ています。
技術の進歩で最も期待している分野がこれです。
星空を撮りやすくなる日が来るのを期待しています。
ニコンD800/D800Eは衝撃的な印象を残したカメラで、明らかにセンサー性能が伸びました。
実際に使っていたD700と比べても、圧倒的に高画素化した上に、さらにダイナミックレンジや高感度にも強くなっていました。
しかしそれから約9年が経っても、センサー性能の根本的な底上げはないように感じます。
これが、私が長らくカメラを買い換えなかった理由です。
そして今回も噂通り、センサー自体の大きな進化を感じることはありませんでした。
感覚値では、D800Eと比べて、ダイナミックレンジは同等程度、高感度性能も同等程度という感じでしょうか。
場合によっては高画素化の影響で低下しているように感じることも。
裏面照射型CMOSセンサーというのも、違いが表に出てきていません。
もうカメラのセンサー技術は頭打ちなのでしょうか。
やはりZレンズの素晴らしさがあるので、センサーが進化した未来に大いに期待したいです。
こちらが最大の魅力になるとは思っています。おそらくニコンさんが命を懸けている部分のはずです。
解像感は実に見事です。絞り開放のF2.8から隅まで十分満足できそうな解像度を誇ります。
どのレンズでも、45MPの高画素化の上で等倍比較しても36MPの旧システムに勝る解像感だと思います。
全体的に1~2段階くらい解像度が鮮明になった感覚があります。
とくにZ70-200/2.8のほうは圧倒的で完璧に感じられました。
少しデカくて重たい以外は申し分のないレンズではないでしょうか。
ここまで完璧なレンズならお高いお値段も納得するしかないかもしれません。
一方でZ24-70/2.8のほうは少しだけ描写が気になります。
基本的には素晴らしい描写ですが、点光源があまり綺麗に描写されない印象です。
F4くらいまでではコマフレアが目立ち像が乱れている印象。
また遠景の木々等は精細に描写しているように見えるものの、富士山の山肌などを見るとやや荒い感じに見えます。
描写の甘さが被写体によって表れてくるような印象。
周辺光量落ちも大きいので星景撮影には向かないかもしれません。
少し評判より悪い印象で、ひょっとするとハズレ個体を引いてしまったのか?と思っています。
なんとなく感覚的には、調整すれば本来はもっと良いレンズなんじゃないかと思ってしまうのですが。
さすがに同じレンズを何本も買って比べるわけにもいかず、今のところ「そういうものか」と飲み込むしかありません。
前評判からするとやや期待外れであるものの、ズームレンズとしては十分すぎる解像度を持っているとは思います。
巷では「Zレンズに外れ無し」というフレーズが出るほどなので、可能ならレフ機でこれらのレンズを使いたいくらいです(構造上、無理)。
Zシリーズになってボディに手ブレ補正機構が入りました。
さらにレンズにも手ブレ補正機構が追加で入っているものがあります。
これが使用してみてかなり強力な印象で、「200mm,F8,PLフィルター使用」等の条件でもほとんどブレなく撮影できるため望遠でも三脚が要らなくなりました。
望遠のZ70-200では、レンズの手ブレ補正+ボディの手ブレ補正が働き、スペック上5.5段分の効果とされています。
Fマウント旧型70-200(手ブレ補正3.5段)はFマウント新型70-200(手ブレ補正4段)よりも効果が低く、さすがにPLフィルターを使うとブレ量産でした。
Zは実際に使用した感覚でも明らかに効き目が段違いに良いです。
望遠でも手持ちでバシバシ撮れるという力を手にして、機動力がより高まりました。
また標準・広角でも絞り込んで手持ち撮影がしやすくなったので恩恵が大きいです。
元々PLフィルター(明るいもの)+手持ちでも最大F13程度で撮っていましたが、さらに絞り込んでの撮影も手持ちで可能になりそうです。
標準のZ24-70のほうはレンズ自体に手ブレ補正が非搭載であるため、ボディのみの動作のよう。
Z70-200ほどの補正効果は確かにないですが、無補正よりは良いです。
Zボディ+Z24-70の場合はボディのみで5段ということでしょうか。
(Fマウントの新型24-70は私は使っていませんが公称4段。)
風景は三脚で撮影するイメージが強いかもしれませんが、手持ちで自由度を高めるのも非常にオススメです。
ここは素晴らしい進化ですね。
三脚が不要になると、天気を見ながら車で移動する場合などに機動力が上がるというメリットもあります。
気になっているのは、キヤノンのEOS R5/R6では手ブレ補正対応レンズとの組み合わせで最大「8段」の手ブレ補正効果があるとして2020年に発売されています。
あまりニコンから鞍替えする人はいませんが、十分魅力のあるシステムだと思って見ています。
はい、これは致命的な問題です。
事前レビューでこのような話は聞かなかったのですが、ピントを外す確率がかなり高いように思えます(体感値)。
AF速度は非常に速くノンストレスです。
Z7のAFは「像面位相差AF」と「コントラストAF」を組み合わせた「ハイブリッドAF」とのこと。
コントラストAFなら精度も高いと思ったのですが、なぜか良く外します。
合う時はピタリと来るので調整は必要ないですが、一方で合焦のサインが出ても少しズレていることが頻繁にありました。
(状況にもよるし感覚値ですが数十回に1回くらい?)
レフ機のときはこのような微ズレは特に明るいシーンではほとんどなかったはずです。そもそもAFの仕組みが違うので、特性は違って当然ですが。
都度確認しないと不安なので、AF使用時でも拡大表示して目視で合焦を確認してからシャッターを切るような撮り方になりました。
「1枚ずつじっくりしっかり撮る」というスタンスで構えればそれもアリかと思いますが、プロが使う機械としては失格のような気がしますね…。
当然ながら被写体によって精度が異なると思います。
被写体は全て遠景の富士山なので、遠くの被写体が苦手なのかなと思っています。
空気が霞んでいたり揺らいでいると、映像からピント位置を正確に見つけるのは目視でも難しい場合もありますので。
極端な逆光・遠すぎる被写体・コントラストが薄いものなどは苦手なように思えます。
レンズはZ24-70、Z70-200どちらでも確認。またPLフィルター使用時のほうが外す確率が高いという感覚値です。
またオススメの設定として、ファンクションキーに「拡大画面との切り替え」を設定すると拡大/復帰が素早くできますので、シャッターを切る前にきちんとピントが来ているを確認するのは容易です。
そもそも、レフ機ではピント確認するためには一度撮影するか、「ライブビュー」モードに入ってから拡大する必要がありましたが、
ミラーレス機では常に電子映像が出ていますので撮影前の確認作業が飛躍的に簡単になったのは大きな恩恵でしょう。
そう思うと「きちんと確認してから撮る」スタイルも受け入れやすいかと思います。
ローライトAFの存在を後から知ったので追記・修正しました。
通常AFではレフ機よりも性能が落ちたように思えましたが、新しく「ローライトAF」という機能が登場しました。
これを設定でONにしておくと、通常AFよりスピードが落ちるものの、暗い状況でもAFが使える場合があります。
ローライトAFを使った場合はD800EよりもAF性能が上がっています。
ただ被写体や微妙な明るさの違いでかなり検出性能が違うので、万能というわけではありません。
ピントをうまく検出できないと、数秒~10秒くらい迷ったりもしますので、逆にストレスとなる場合も…。
ローライトAFを使用時も、やはりちゃんと合焦していない場合があるので、ミスしたくない場合は拡大表示での確認が必要でしょう。
また、夜景などの点光源でのAFについては、D800Eではかなり信頼度が低く使わないほうが良かったのですが、
Z7では、外すケースもあるものの、合ったときはかなり精度が高く、実用性が高いと思いました。
きちんと確認していれば、夜景などの点光源でのAFも使えそうな感じです。
まだあまり多くのシチュエーションで試せていないので、引き続き様子を見たいと思います。
私としてはパナソニックのミラーレスを使っていたときに経験済みのEVF(電子ファインダー)。
あの時から特別な不便は感じていませんでしたが、今回のニコンミラーレスも違和感なしです。
光学ファインダーと電子ファインダーはそもそも根本から仕組みが違うわけで、この「違和感がない」というのは素晴らしいことなのかもしれません。
光学ファインダーのほうが見ていて気持ちが良いのは事実です。
一方で電子ファインダーのほうが撮影後の画像に限りなく近いものを見られるので、結果に拘る場合にはEVFのほうが適しているとも言えます。
ただ、電子映像なので少し目が疲れる印象があります。
これはミラーレスカメラの構造上、当たり前中の当たり前なのですが、少しだけ不便に感じます。
電源を入れてから立ち上がるまでにややタイムラグがありますし、待機状態になっている場合もボタン等を押して復旧させなければなりません。
また長時間露光をして「長秒時ノイズ低減」を実行中もファインダー確認ができないため、処理中に次のカットの構図を決めるということもできません。
まあこれは機械の構造上仕方ないので、素直に諦めるしかないと思っています。
撮影した画像を確認することもできますし、撮影後の仕上がりを確認しながら構図を取ることもできます。
「Lvに撮影設定を反映」という項目があるのでONにしておくと、設定のミスが減るでしょう。
レフ機では光学ファインダーなので、どうしても肉眼でのイメージ通りに画像が出てこないケースがあります(とくにハイコントラスト・逆光などの場合)。
電子ファインダーではそういったギャップがかなり減るので、ミスの少ない撮影をするには良い機械だと思います。
暗所でも明るく見る方法が分かったので追記・修正しました。
噂では暗所でも見やすくて良いと聞いていたのですが、使ってみたところ、そうでもない。
ファインダーを覗いた時、肉眼より良く見えるか否かがひとつのポイントだとは思います。
(EVFなので背面モニターも同様です。)
結論から言うと、普通に使っていると暗所には弱いが、「プレビュー」によって明るくすることができます。
Z7では、普通に使っていると、暗いところで星空などを撮りたい場合に、肉眼よりも見えないので構図が取れません。
D800Eの光学ファインダーでは、F2.8のレンズを付けていれば普通に肉眼と同等に見えました。
夜でも富士山がどこにあるかは分かります。
明るくするための設定も見当たらず困っていましたが、「プレビュー」ボタンを使うことで画面が明るくなることが分かりました。
絞りを開け、ISO感度を上げる等して、明るく撮れる設定にする必要がありそうです。
その状態でFnキーなどに割り当てた「プレビュー」ボタンを押すと、押している間はファインダー/モニターが明るく表示されます。
ファインダー像が暗くて困るケースはあるはずなので、もう少し分かりやすい方式を導入して欲しいですね。
ミラーレスカメラの特性上、プレビューの必要性をあまり感じなかったので最初はファンクションキーから外していましたが、必要なので戻しました。
それでも肉眼よりはやや見づらい印象で、画面はかなりノイズがうるさくなるため綺麗な映像ではありません。
光学ファインダーの方が見やすいのは間違いないです。
Z6のほうが感度が1段ほど高い仕様なので、Z7よりもよく見えるかもしれません。
なおソニーのミラーレスでは「ブライトモニタリング」という機能があり肉眼以上に見えるそうです。
ソニーのカメラはそもそもセンサー自体が高感度に強いと言われていますが、ニコンにも分かりやすい設定を導入して欲しいですね。
具体的には、レンズキャップを外した場合です。
電源ONの状態でレンズキャップをしていて、そこからキャップを外すと露出が急激に変わるため、明るさが調整されます。
これが2~3秒くらい掛かるので、かなり待たなくてはいけません。
(ファインダーも背面液晶も同様。)
先にレンズキャップを外した状態で電源をONにすると問題ないので、後から外す場合のみ余計に待たされる事になります。
光学ファインダーのない、ミラーレスならではの問題です。
太陽光などでセンサー焼けしないようキャップをすることもあると思うので、制御でうまいことやって欲しいです。
タッチパネル操作には期待していましたが、微妙な仕上がりだと思います。
レフ機のD800EやD810は非対応で、D850からは対応していました。
特に残念だったのは①タッチによる画面の拡大ができないこと、②タッチでシャッターを切るとAFが動いてしまうことですね。
①ついて、タッチでAFのみを動かすことはできるので、それによりフォーカスポイントを選択後、手動で拡大表示にすることはできます。
しかし無駄にAFが駆動してしまいスマートではなく、暗い状況などで合焦しなかった時に元々のピントからズレてしまうこともあります。
ピントを「合わせるため」ではなくピントを「確認するため」に位置を選択したいのです。
結局、確認したい場合はセレクターでせっせと位置合わせをしています。
②ついては、AFを切ればタッチでシャッターのみになるのですが、
やりたいことは「親指AFでピント合わせ後、画面タッチでシャッター」なので、いちいちAF/MFのり着替えが必要では面倒です。
画面タッチでシャッターを切りたい理由は、ブレ防止が主な理由なので、レリーズを使うなりディレイを使うなりで対応しています。
タッチでシャッターのみができれば、3つ目のブレ防止の選択肢になります。
一方、画像を確認する場合はGoodです。
画像再生ではダブルタップで任意の場所を拡大表示できるので、ピントやブレの確認が素早くできます。ナイス!
その際、画面の下の方をタッチするとスクロールバーのような物が出てきて邪魔になります。これは個人的には要らないです。
二本指で拡大したり、スワイプすることもできますが、iPhoneのようなスムーズな動きを期待してはいけません。カクカクです。
操作にタイムラグもあります。
しかしスマホの画面とは方式が違うため、手袋をしていても操作できます!
シャッターに関連していくつかポイントがあるため1つずつ解説します。
1つは『サイレント撮影』。
”サイレント”という名前なので「音が出ない」ことが押し出されたネーミングになっていて、AFの合焦音が消えたりもするのですが、その本質はそもそものシャッター機構の動作の違いです。
電子シャッターとなり物理的にシャッター幕が動かないため、①まったく振動がなくブレない、②太陽などの光源がシャッターに反射しないという恩恵があります。
なお、風景撮影では「ローリングシャッター歪み」はほとんど気にならないと思いますが、「長秒時ノイズ低減」が利かなくなることには注意です。
また室内撮影では照明のフリッカーが縞模様で写るケースがあります。
なおD800Eでは電子シャッター機能はなし、D810では「電子先幕シャッター」が搭載、D850で「電子シャッター(先幕も後幕も電子)」が搭載となったようです。
昔からあっても良さそうな機能だとは思いますが、ようやくこの機能を手にしました。
とにかく、望遠撮影でシャッターブレを気にしなくて良いのが有り難い。
あとは純粋に、静かに撮影できるのも良いと言えば良いです。
本当に全く音がしないので、自分でも撮っている感じはないし、隣で誰かが撮影していても全く無音ということで少し不気味です。
一眼レフの独特のシャッターを切る楽しさは、無くなっていきますね。
一眼レフではミラー動作(ここが一番音が出る)+シャッター動作の音がありました。
今回のZ7ではミラーはそもそも無く、シャッターの動作も無くすことが可能ということです。
また、個人的に重要だったのが、②の太陽を撮影したときに上下に出るフレアーのような反射が出なくなるということです。
これは絞りがF10以下くらいのとき、とくに絞りを開けたときに目立つのですが、太陽が上下に光を反射して滲む現象があるのです。
これはミラーやシャッターを上げた状態では写らないので、レンズのゴーストやフレアーではないことは分かっていました。
ミラーアップをしても発生するので、ミラーのせいでもないことが分かっていました。
その正体はどうやらシャッター幕の反射だったようで、今回、初めてサイレント撮影によりシャッター幕が動かない撮影をしてみて、その反射が消えることが確認できたのです。
このお陰で絞り開放などで太陽を撮ってもうるさい反射がなく、綺麗な描写になりました。これは大きいです。
サイレント撮影は素晴らしい。
D800Eにはなかった「露出ディレー」機能がD810から搭載されています。
【訂正】D800Eにも搭載されていましたが、使用したことがありませんでした。
D800/D800EやD810では1~3秒、D850やZ7では0.2~3秒の間で、シャッターを押してから撮影までのタイムラグを出してくれる機能です。
これにより、三脚撮影時のブレを抑えることができます。
これまではレリーズを使って、カメラに触れないようにして撮影するのが当然でした。
三脚を立てたらレリーズも用意して接続するのが基本。
Z7を購入後、端子がD800系とは異なるため、レリーズも購入しました(いつも互換品ですが)。
D800系の丸形の10ピンターミナルはボディの正面に接続口があり、しかも接続方向に対してケーブルが直角に出ているので、収まりがスマートだし引っ張っても外れたり折れたりする心配がありませんでした。
一方で10ピンではない端子(名前ある?)は接続方向にまっすぐコードが伸びる形状で、昔D7000を使っているときに横に引っ張って壊したこともあった。
またボディの横に飛び出す形になるので非常に収まりが悪い。
そういうわけでレリーズケーブル周りでも不満を持っていたのですが、ディレー機能があることに気付いてからは、レリーズを差すことがほとんどなくなりました。
基本的には三脚撮影時は「1秒」のディレーを設定することで、指でシャッターを押してもブレる心配はありません。
これまではセルフタイマーの2秒を使うこともありましたが、補助光が光ったり音が出たりと弊害があり、また2秒は少し長すぎます。
ディレー機能はおそらくブレの為にある機能で、需要に合致しました。
また、秒数を細かく設定できるのもGoodです。
不安なら3秒ディレイとすれば三脚のブレはほぼ確実に落ち着くでしょう。
それでもなお不安だったり、確実に三脚を動かしたくない場合にのみ、レリーズを接続すれば良いのです。
レリーズの準備と抜き差しが不要になったことで、カメラのセッティング・撤収が素早くなったということはかなり大きいです。
無駄なことに手間を掛けたくない。基本的にかなり面倒くさがりな性格なんですね。
ただ1秒ディレイすればタイムラグが1秒あるので、シャッターチャンスを逃す恐れもあり、本気で集中して撮影したい場合、レスポンスが求められる場合などは、やはりレリーズが必要となります。
これは、ないよりは良いですがさほど大きなインパクトはない印象でしょうか。
レフ機のD850には搭載されています。
「バリアングル」式ではなく「チルト」式と言うようです。チルトは自撮りはできません。
画面の角度を変えられるようになったため、極端なハイアングルやローアングルで映像を確認しながら撮影できるようになります。
ハイアングルが必要なら脚立に乗り、ローアングルが必要なら地面に這いつくばれば良いので、どうしても必要な機能とは言えない気がしますが、あれば便利です。
実際に、脚立などを持っていない状況で、ハイアングルが撮りたくなれば、両手を目一杯上に伸ばして撮影する、などということができます。
準備なしでも気軽にハイアングル・ローアングルが試せるので、新しい構図や撮り方が生まれる可能性がありますね。
前景を入れての撮影の場合、「脚立を出すのは面倒だけど、少し上のアングルから撮りたいとい」うことはけっこうあります。
Z7ではメモリーカードとしてXQDカードが採用されています。
2012年のNikon D4から採用されている比較的新しいメディアです。
これまではコンパクトフラッシュ(CFカード)を使っていたので、メディアも新たに必要となります。
メディアとしては高額な印象で、中古品で2枚と、カードリーダーも合わせて購入しました。
大きさはSDカードよりも少し大きく、厚みがSDカードの2倍くらいで、絶妙なサイズ感のメディアです。
私は動画撮影や連写はしないので、撮影時はとくに何も感じませんが、PCにデータを取り込むときに驚きました。
仕様上、CFカードの3~4倍くらいのスピードがあるようなのですが、取り込みが非常に早かったです。
画素数も増えてデータサイズは巨大化していますが、スピーディに取り込みできました。ここはストレスがかなり減りましたね!
なおシングルスロットを採用したことでユーザーからの不満が続出し、後継のZ6IIやZ7IIではSDカードとのXQDのダブルスロットが採用となりました。
個人的にはこれまでもメディア1枚しか使用していなかったので、シングルスロットで問題ありません。(XQDカードを家に忘れたらアウトかも!)
ミラーレス機と言えば、気になるのがバッテリーの持ちです。
ファインダーや液晶に映像を映すために、常にセンサーから光を取り込んでいる状態です。
レビューや噂を聞く限りでは、ニコンさんは控えめに見積もって数値を出しているが、「実際はかなり撮れる」という感じでした。
実際に使ってみてどうだったかと言うと、確かにそれなりには撮れると思います。
ただ、レフ機と比べてしまうと、やはり消耗が早いですね。
個人的には、レフ機での「昼間ならほぼ無尽蔵に撮れるぜ」というあの感じは好きだったので、少し残念です。
予備バッテリーは常に持ち歩く必要があると思います。
最近は長期間の撮影の旅はあまりしませんが、しばらく充電できない環境の場合は不安かもしれません。
なお、操作しないと30秒で待機状態に入るのがデフォルトだったと思いますが、20秒にして電力消費を抑えるようにしています。
(再起動時に電力食うってことはないよね?)
Z7になり、レフ機とはバッテリーが変わるものだと思っていたが、実は互換性があり共用で使えることが分かりました。
D800Eのバッテリーは「EN-EL15」、Z7のバッテリーは「EN-EL15b」。
なおD810はD800Eと同じ、D850は「EN-EL15a」または「EN-EL15b」、Z7IIは「EN-EL15c」とのこと。ややこしいですね。
見た目の色や型番は違うバッテリーですが、形は同じで、以前のレフ機のバッテリーも使用可能。
最大で5~6個くらいの予備バッテリーを持っていたので、これは助かります。
ただ、新バッテリーの方が持ちが良いとらしいので、もし旧バッテリーの持ちに不満を感じたら、最新のバッテリーを予備でも買い揃えたほうが良さそうです。
2ヶ月使ってみて、確かに新バッテリーのほうが持つような気はしますが、2倍とか大きな差はないような感覚です。
大きく見積もって1.5倍くらいの差でしょうか。
あとは気になるのは、バッテリーチャージャー(充電器)のコードが付属していないのでコンセントに直接差すタイプになっていること。
形状として使いづらい感じです。
無印~bまでは同じ容量1900mAhで、cのみ2280mAhに容量アップしているようです。
無印~bまでは同じ容量にも関わらず、Z7で無印やaを使うと、bよりも減りが早いと公式に書いてあります。
またbについては、調べると色が黒いものとグレーのものがあり、私のZ7に付属していたのはグレーでした。混乱します。
基本的に全てのバッテリーやチャージャーは相互に互換性があると考えて良さそうですが、カメラ本体を接続しての充電は成約があるようです。
(私はバッテリーを外して個別でしか充電しないので問題なし。)
ここもカメラの核心部であり、重要なポイントです。
実はニコンはD800/D800Eの後から色作りを変えたという話は知っていました。
知人からももD810、D850では赤色の発色が綺麗に出ないと聞いていました。
赤や黄色が強い傾向から、緑や青の発色が良くなったとの話でした。
今回、確かにその傾向が感じられた気がします。
同じ被写体で正確に比べたわけではないのですのが、何度も撮影を重ねる上でその印象は確かにありました。
朝焼けに染まる富士山の「紅富士」の色があまり綺麗に出ないなと。
肉眼で見る「赤の鮮やかさ」がちっともカメラに反映されなくてガッカリもしました。
iPhoneのほうが綺麗に撮れているんじゃないかと。
今回のシステム変更では、現像に使うソフトもLightroom 4からLightroom Classicに変更しているので、その影響も多少あるかもしれません。
微妙な色味の違いは、現像時に調整することで補えるとも言えるかもしれませんが、今のところ、現像時に調整しても少し違和感を感じています。
しかしまだ「気のせいかもしれない」という領域を脱していません。
同じ被写体をじっくり撮り比べて、厳密に比較しないと答えは出ないかもしれません。
「現像で何とでもなる」問題なのか、「根本的に色がうまく出ない」なのか、じっくり考察する必要がありそうです。
もし後者であれば、根本から考え直さなければいけない事になります。
なお色以外の部分(コントラスト等)においても、なんとなく違いを感じますが、まだ言葉で表現できるほど掴めてはいません。
レンズもボディも違うので差はあるはずですが、大きな差ではないと感じています。
D700からD800Eにしたときは大きく変わりました。
少しマニアックな内容になってきます。
周辺光量落ちが激しいと補正するのが難しくなります。
Z24-70は開放のF2.8で、Fマウントの24-70よりも激しく周辺光量が落ちます。
開放で使った場合はかなりキツイ暗さになります。
そしてそれ以上に問題なのが現像ソフトのLightroomで十分な補正ができないこと。
私の環境(Lightroom Classic)でですが、Zレンズのプロファイルは適応できず「内臓プロファイル」を使うしかなくなっています。
しかしこの内臓プロファイルを適応してもヴィネットが完全に補正はされません。
また、撮影時の設定を反映しているようなので、撮影時に補正を「強め」に設定すべき状態となっています。
(周辺光量をあえて落としたい場合はレンズの描写に頼るのではなく後補正するほうが融通が利くと考えています。)
Fマウントシステムの場合はいったん完全にフラットにすることができたので後の調整が自在でした。
Zマウントシステムでは実質的に、開放付近で撮影すると調整しづらくなるため、絞る必要が出てきてしまっています。これは勿体ない。
LightroomさんはなぜZレンズのプロファイルに対応しないのでしょうか。
詳しい方がおりましたら教えて下さい。
またニコン純製ソフトのCapture NX-Dを使っても完全にスムーズに補正はできず、ヴィネットの扱いが厄介になっています。
Z24-70の光量の落ち方の酷さもあり、ちょっと開放付近では扱いづらいなという印象です。
一方、Z70-200のほうは調子が良いです。
Fマウントに比べて絞り込まなくても周辺光量の落ち方が穏やかで目立ちにくく感じます。
Fマウント70-200では、F8~F11あたりでもまだ周辺光量落ちが気になるため基本的にF13まで絞って使用していましたが、
Zマウント70-200になるとF8でもかなりフラットな画像が得られるため、撮影がだいぶ楽になりました。
シャッタースピードの面でも、解像度の面でも、センサーゴミの面でも救われます。
「基本F13で撮る」というのはなかなかの重荷でしたからね。
ヴィネットの問題は意外と地味ではありますが、仕上がりを左右する大事なポイントだと思っています。
そういえばセンサーが小さいカメラだとあまり悩みがなかった気がします。大口径で問題になりやすいようです。
ヴィネットに限らず、RAWで撮影した画像については、撮影後にパラメータを変更できるのがこれまでの基本的な考えでしたが、
内蔵プロファイルの使用によって、撮影時に設定した設定が後では調整できないことになり、常識が変わりました。
まだ細かい仕様などは分析できていません。
カメラメーカーはあまり考えてないような気がしますが、風景カメラマンとしては重要なポイントとなる部分です。
まずZレンズの仕様として基本的に絞り羽9枚で、最近のレンズはほとんど奇数絞りになっているのが残念でなりません。
ボケを綺麗にするためのようですが、パンフォーカス風景がメインで太陽や夜景を撮る場合には偶数絞りの需要はかなりあると思います。
選べるようにならないかな…。
光芒(光条)の出方は、Fマウントのレンズよりだいぶソフトになりあまりトゲトゲしていません。
ちょっとインパクトに欠ける描写で、個人的には残念です。
光芒にインパクトを出したい場合はFマウントレンズを使う選択肢も有り得そうです。
またゴーストはあまり酷くは出ず、割と控えめな印象で、Fマウントレンズより改善している印象です。
Z24-70では青い点状のゴーストがぽつっと出るのでうまく消去できないと妙に違和感が残るかもしれません。
Z70-200のほうも、比較的逆光には強いように思えますが、ゴーストは普通に出ます。
またおそらくセンサーの反射と思われる模様が、Z7ではD800Eと比べると出やすくなっているように思えました。
これはデジタルカメラの欠点なんですよね。
センサーの仕様が変わったのかもしれませんが、なんとかして上手く防ぐ方法はないのかと思ってしまいます。
センサー反射が出づらいカメラがあれば逆光専用に買っても良いくらいです。
逆光時の撮影は、太陽高度や大気の霞具合でかなり条件が異なってきますので、改めて検証していきたいと思います。
正直、期待していた機能なのですがあまり使っていません。
設定が分かりづらいですが、カメラとスマートフォンを接続した上、スマホ側からの操作でRAW画像を取り込むことができます。(知人に教えて頂きました。)
まだ試していないのですが、スマホでのRAW現像にもこれから挑戦したいです。
結局今のところは、家に帰ってからPCで現像しています。
また、スマホと連動させることでリモート撮影ができます。
超ハイアングルなど、目の届かないところまでカメラを動かして撮影する場合や、三脚で固定して車の中から撮影など、色々用途はあると思います。
ただ、そこまで使う機会は多くないのが現状です。
また、モードやISO感度に成約があるなど、ソフト的な柔軟性がまだまだ悪く、普通にカメラを使うように撮影することはできません。
優先度が低い機能だったのかもしれませんが、ちょっと作り込みが甘いように思えます。
ニコンさんは技術屋であり、まだまだITには弱いのかなと感じてしまいます。
ミラーレスカメラは、センサーの前にミラーがなく、なぜか電源OFF時にシャッターも開いている機種がほとんどです。
キヤノンのEOS Rシリーズは電源OFF時にシャッター幕が閉まることで好評のようです。
ソニーも最近になりこの機能を追加してきましたね(なんとソフトのアップデートで!)。
レフ機に比べてミラー+シャッターの2つの壁がないので、かなりゴミは入りやすいと予想していました。
結果ですが、2ヶ月使ってみて、やはり汚れやすかったです。
レンズ交換の頻度が高かったことも影響しているので、厳密な比較はできませんが。
基本的にはやはり「レンズを極力交換しない」のが最も効果的です。残念ながら。
また絞りを絞っての撮影があらかじめ分かっているときは、事前に清掃するしかないでしょう。
この2ヶ月間、ボディ1台に対してレンズ2本を主に使って撮影していたので、レンズ交換がかなり多かったです。
個人的な考えですが、やはりボディは2台あったほうが便利です。レンズを交換する手間とリスクを極限まで減らしたいです。
2ヶ月の使用後、自分でセンサークリーニングを行いました。
クリーニングにはスワブタイプのものを使いますが、なんとD800Eに比べてセンサー面積が大きくなっていて、幅が合いませんでした。
仕様を見るとD800Eは「35.9×24.0mm」、Z7は「35.9×23.9mm」と、僅かに小さくなっているのですが、実際の平面としては大きくなっていました。
予想ですが、センサークリーニングをしやすいように、センサーがない部分にも表面素材の面積を追加したのではないかと思っています。
【追記】電源ONの状態でバッテリーを抜き差しするとシャッターが閉まった状態に固定されるとの情報を頂きました。
非公式っぽい方法なので自己責任となりますが、レンズ交換の際はこの方法は大いに使えそうです!
上述の通り、素晴らしい手ブレ補正性能を発揮してくれるのは良いのですが、Fマウントの時のようにレンズのスイッチで設定を切り替えることはできなくなりました。
手ブレ補正のON/OFFを切り替えるはメニューから切り替える必要があり、よく使う項目を登録できる「iメニュー」に手ブレ補正の項目を入れ込んだとしても、iメニュー呼び出し→手ブレ補正の項目をセレクト→設定を変更と3ステップあり、直感的でもないのでスムーズには行きません。
当然ながら三脚に乗せているのに手ブレ補正ONなどの状況ではブレてしまう可能性もあるし、三脚から手持ちに切り替えるときに素早く設定を変更できないのは、致命的です。
これはヤバイと思ったのですが、解決する方法がありました!
それが、ユーザーセッティングを使って「手持ち用の設定」と「三脚用の設定」を登録することです。
レフ機の時代はユーザーセッティングは使いませんでした。必要がなかったとも言えます。しかし今回は必須でしょう。
ユーザーセッティングに設定を登録すれば、ダイヤルをひとつ回すだけで一気にカメラの設定を変更できます。
私の場合はU1=手持ち用、U2=三脚日中用、U3=三脚夜間用という設定で登録をしました。
どこまでの設定が記憶されるかなど細かいクセがあり混乱するかもしれませんが、ユーザーセッティングを使いこなすとかなり便利になります。
ここからはソフトウェア面での不満が続きます。
ニコンにとって初代のフルサイズミラーレスということもあり、ソフト的な使いづらさが多々出てきています。
まずは衝撃的な残念さだったのが、電子水準器。
D800Eでは、グリップしながら右手で押せるファンクションキーにファインダー内水準器表示を割り当てるられたので、ファインダーを覗きながら水平確認ができました。
ファインダーの下部に小さいゲージが出るだけなので、覗いている映像を邪魔しません。
ところがZ7の水準器は画面の中央にデカく表示することしかできず(ファインダーも液晶も共通)、被写体に被ってしまい邪魔です!
しかも表示を切り替えるためにはDISPボタンを何度も押すことになるので非常に面倒ですね。
手持ち撮影で水平と構図を同時に取りたい場合には明らかに使いづらいものとなってしましました。
小さい表示なら常に表示してあっても邪魔にならないくらいなんですけどね。
改善要望を出したいですね。
また、そもそも電子水準器の精度自体が少し怪しい印象を受けています。これは以前からのことですが。
電子水準器はそもそも信用しすぎず、参考程度に使って、現像時にきちんと補正することが大事です。
これは説明書にも書いてあり、仕様のようです。
電源を一度OFにすると設定したピント位置がズレてしまいます。
(調べるとレンズの特性のようで、他社カメラでも同様の現象があるようです。)
風景撮影ではほぼピントは無限遠に固定で、夜景などではマニュアルで慎重にピント合わせをしたりします。
それが電源を切ると台無しに。最初はかなりイラッとしました。
なので、基本的には撮影を少し休むときは電源を切らず、自動で待機状態に入るのを待つことが多くなりました。
バッテリー消耗が大きいので早くOFFにしたい気持ちがあるのですが、ピントのために切らずに待ちます。
一番イヤなケースは、長時間露光中に例えば三脚を蹴ってしまうなどのトラブルがあり、撮影を一時中断したいときです。
長時間露光や長秒時ノイズ低減を途中で中断するには、電源を切るしかないので、ここでピント位置がズレてしまいます。
最悪です。
かなり残念な仕様となっていますが、後継のZ7IIではピント位置を保存する設定が追加され、改善されたようです。
ここからは細かい不安点を一気にまとめて。
ニコンさんはまだまだソフト分野は強くない印象ですね。
実際に使ってみると気になる点は続々と出てきます。
しかしソフト面の問題は、ファームウェア(ソフトウェア)アップデートで改善できるはずですし、基本的にはアイディアさえあれば実現できるものなので、今後の改善を強く期待しています。
が、撮影のブラックアウトが終わったあと、一瞬だけリアルタイム画像がチラッと出たあと、撮影画像に切り替わります。
そのちらっと出るやつ、要らないですよね…すぐに撮影画像を出して欲しい。
どうも画像の書き込みや、画像として出力されるまでにタイムラグがあり、その間にリアルタイムの映像が表示されるようです。
ファインダーで見ていてもチカチカするので最初はかなり嫌でした。
また、「撮影直後の画像確認」を「する(画像モニター表示のみ)」にした場合に、撮影後にファインダーから目を離した場合ではモニターに再生画像が表示されません。
この動作はレフ機では一般的な動作なので、動き物を撮りながら確認するということができなくなっています。
風景メインならあまり問題ありませんが、使い方によってはかなり困るかもしれません。
設定の名前は「半押しタイマー」と言って混乱を招くネーミングとなっていますが、
一定期間操作をしないと待機状態になる設定です。
ミラーレスカメラは撮影していない間にもどんどん電池を食うので、一定時間が経過したらパワーオフにする機能は必要です。
ただ、ファインダー覗いてるときに切らなくてもいいじゃん!て思いませんか。
じっくり構図を決めていたり、フィルターの効き具合を調整している間に、パワーオフになってしまいます。
ファインダーの横にはセンサーが付いていて、顔を近づけると表示を切り替えるような仕様があるので、ファインダーを覗いているかどうかはカメラは知ることができます。
「何も操作していない」の判定方法を改善してほしいです。
このため写真全体の構図が崩れてしまい、撮影画像の構図をを正しく評価できません。
ちょっと信じられない表示方式です。
メニューをカスタムすることで「画像のみ」の表示(情報なし)を追加することができるので、そちらで確認するようにしています。
このデフォルトの情報が被るスタイルは、非表示にしたいのですが、消すことはできないようです。
ファインダー/モニターとも、反映されるの絞り値は開放からF5.6までとのこと。
それ以上絞り込んでも、実際にシャッターを切るまではF5.6の映像となります。
「Lvに撮影設定を反映」の設定をしてもダメです。
プレビューボタンを押すことで絞り込んだ表示に切り替えることができますが、
押している間だけの反映のため、拡大しての確認は不可です。
レフ機のライブビューで出来たことがなぜできないのでしょうか。
絞り込んだ上でピントを確認することができません。けっこう酷いです。
最後はちょっと愚痴の連発みたいになってしまいました…。
さて、長々と書いてきましたが、最後にまとめたいと思います。
やはり当然ながら機材というのは買って使ってみないと分からないことが沢山あります。
ネットのレビューや知人の口コミは大変役に立ちますが、最後に判断するのは自分の感覚です。
今回の生々しいレビューが参考になれば幸いです。
・素晴らしいZレンズ群
・機能的な多くの改善(機動性・利便性アップ)
・センサーはあまり変わらず(将来に期待)
・ソフト的な数々の小さな不満がある
・いくつかのハード的な問題もある
今後も使用しながら追求していきたいと思います。
私としても今回の記事を作成しながら、改めて調べて気付いたり学んだことや、他社の機材について知れたことがあり、レビューにトライしてみて良かったです。
カメラ機材は高額でなかなか色々な物をテストするのは難しいのですが、またチャンスがあれば他のメーカーも使ってみたいですね。
また一つの機材に拘ることなく、シーンに応じて複数の基材を使い分ける必要もあるでしょう。
富士フイルムのGFX50やGFX100、キヤノンのEOS R5、ソニーのα7RIV等も一度は使ってみたい機材です。
もし機材投資の元が取れる境遇になったなら、手にしてみたいと思っています。
(注)今回の記事は、初回「写真・画像なし」でお届けしております。
後日写真と画像を追加する予定なので、更新をお待ち下さい。
最後までご覧いただきありがとうございました。
(記事を書くのに丸3日掛かりました。)
久々に機材を乗り替えたので、これまでと異なる点について色々と目についてしまいました。
ブログやツイッターで愚痴るのは簡単ですが、せっかく調べてまとめたので、ニコンさんに要望を出そうと思っています。
調べたところ以下のフォームが見つかりましたので、改めて内容を整理してから送信する予定です。
(愚痴るだけじゃなくて行動しましょう!人生の基本!)
https://www.nikonimgsupport.com/nij/NIJ_ask_support
技術的なものやハードウェア的な面では改善が難しいかもしれませんが、ソフトウェア的な部分はやるかやらないかというだけなので、比較的改善のハードルが低いと思っています。
とくに「ファームウェアアップデート」という方法は古くから定着しているので、これを使って使い勝手をバシバシ良くして欲しいと願います。
本気で写真を撮るからこそ、無駄な操作はしたくないし、自分好みにカスタマイズしたいのは当然です。
1秒のシャッターチャンスも逃したくないです。
他社の方が使い勝手が良かったら、ユーザーは乗り替えてしまいます。
機能や操作が不便だったら、スマホでいいやという気になってしまいます。
ニコンのカメラがより良い製品になりますように。
おわり
超久しぶりにブログ発信をします。
今回、思い切ってマウント変更して撮影機材を一新したのでレビューすることにしました。
撮影機材ってなかなか簡単に買えないものなので、実際に使ってみた人のレビューがあると有り難いものですよね。
自分自身も、いわゆる”レフ機”から”ミラーレス”へ初めて移行するにあたっては、かなり使い勝手が変わるんじゃないかなど不安があったので、記録として残しておきたいと思いました。
今回は主にニコン「Z7」の内容となるので、同時発売のZ6や、後継のZ7II、Z6IIをお使いの方にも大いに参考になると思います。
乗り換えの経緯は
私は2012年4月に発売されたニコン「D800E」を夏に購入してからは、一貫してこのカメラを使い続けていました。
当時、同じフルサイズのD700を使っていましたが、乗り換えたときの描写の進化(精細さとダイナミックレンジ)には感動しました。
あれから8年以上、中古で買い足しながらなんと計5台のD800Eを手にすることになります(常用2台体制)。
実は5台目(5代目)のD800Eを買ったのは最近でした。
それが中古で買ったものの、広角レンズでの描写に甘さが見られ、マウント部の歪み等があると考えられました。
もう古いカメラを中古で買い続けるのは限界かと感じた瞬間でした。
また、以前から愛用していた大三元の70-200mm/F2.8(VR II)レンズを、誤って落下させてしまったことも影響しています。
ニコンの修理に出して戻ってきたのですが、ピントがズレた状態のままで、再調整してもらっても改善せずでした。
メーカーのちゃんとした修理でもダメということは、諦めろと?
また描写においても、ショックの影響か以前より甘くなっているように感じられ、
やはり衝撃を与えてしまった機材は修理しても本来の性能には戻らないのかもしれないと感じてしまったのです。
なお、最も使用頻度の高かった大三元の24-70mm/F2.8レンズも幾度となく修理送りとなっています。
(最後の修理でかなり良くなって戻ってきた感じがしています。)
長く撮影活動をしていれば機材へのダメージはある程度は仕方なく、そろそろ一新かな、というところでした。
手持ちの機材への不満が(自分のせいで)溜まりに溜まった結果の乗り替えとなったのです。
新しい機材は気を引き締めて注意深く使用しようと誓いました。
なぜZ7にしたのか
今回、機材を新調したのは2020年11月です。
カメラはニコンの『Z7』を選びました。
実は、次に狙っていた機材はFUJIFILMの中判ミラーレス・GFXシリーズ(GFX 50S、GFX 50Rなど)でした。
どこまでも最高の描写を追い求めたくなりますね。
ただこれまでいわゆる”大三元”を愛用してきた身からすると、フジ中判のレンズのラインナップ的には使い勝手がかなり心配でした。
F2.8の明るさが欲しければ単焦点しかないし、ズーム域も狭くて頻繁にレンズ交換が必要になってしまう。
また、被写体として花モノ(前景のお花など+富士山)を撮る場合は被写界深度の浅さが裏目に出ます。
お値段もかなりなので諦めていましたが、そこに飛び込んで来たのがニコンZシリーズの評判でした。
噂によれば、Zのレンズはスゲェということでした。
どうもニコンさんはミラーレス開発にあたって過去のFマウントを思い切って捨て、大口径のZマウントを新しく作った。
その大口径を生かしたレンズがあまりにも素晴らしい、というのです。
中判カメラに求めるのはやはり描写(解像力)がメインなので、レンズがそれだけ素晴らしいなら中判に太刀打ちできるのではないか、と考えました。
当然、ずっとニコン使いなので操作性を考えればニコンで乗り換えるのが一番シンプルです。
また、今までと同様のスペックの”大三元”がちょうど出揃ったタイミングとなり、これまでの使い勝手をそのままミラーレスに移行することができます。
ということで、決めました。
また購入当初は、後継機の『Z7II』が発表されたところでしたが、その仕様がZ7とほとんど変わらないようなものだったので、ならば値下がりしたZ7のほうが狙い目だろう、と考えました。
なおニコンのミラーレスにはもうひとつ『Z6』がありましたが、私の撮影は風景がメインで解像感を重視しており、既存機材のD800E(3630万画素)より画素数が下がるというのは考えられませんでした。
よって4575万画素のZ7をチョイスし、その画質に期待することにしました。
今回購入した機材はカメラボディ1台=Z7とレンズ2本=Z24-70mm/F2.8、Z70-200mm/F2.8。
レンズに関しては、本当は大三元を全て揃えるのが理想でしたが、あまりにも高額なので、これまで使用頻度が高かった標準と望遠の2本をチョイスです。この2本があれば8~9割の撮影に対応できるイメージです。
今回の機材投資に際しては、2021年版カレンダーの売上や、皆様から頂いた多大な寄付を元手として充てさせていただきました。
コロナ禍の中、この鞍替えの決断に踏み切れたのは間違いなく支援して下さった皆様のお陰です。
なお”ミラーレスデビュー”と書いたのですが、2011年にニコンD700を買うまではPanasonicの「GH1」を使っていましたので、実はミラーレスは初めてではないのです。
嘘付きましたごめんなさい。
それでは本題のレビューに入ります。
今回の機材レビューについて
(いったん先行公開ということで、画像なしのレビューをお送りします。後で写真や画像を追加します。)
今回の機材購入は2020年11月で、この記事を書いているのが2021年1月です。
ちょうど丸2ヶ月くらい使用したことになります。
この2ヶ月間は、新しい機材に慣れるため、また使用感を掴むために、普段より積極的に撮影に出ました。
やはり新しい機材を持つと気持ちも上がり、精力的になれる部分もあります。
長年やっていると、マンネリ解消に機材を替えるというのも大事になってくるかもしれません。
そして最も大事なポイントですが、あくまで乗り換え前に使っていた機材との比較がメインであることと、使用者(=私=オイ)の主観であるということです。
またこれも大前提ですが、私は富士山専門の写真家ですので、屋外の風景や富士山をメインに撮影することが前提となります。
そしてスチル(静止画)オンリーで、動画やタイムラプスは撮影していません。
情報を整理すると、旧機材がFマウント(一眼レフ機)で
・ニコン D800E
・AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED(旧型)
・AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II(旧型 VR II)
新機材がZマウント(ミラーレス機)で
・ニコン Z7(初代)
・NIKKOR Z 24-70mm f/2.8S
・NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
です。
なおD800Eの後にニコンからは後継機としてい一眼レフのD810、D850が発売されていますがそちらは使ったことがありません。
性能・機能的に大きな差がなく、あえて新製品を買わずともD800Eで満足していたためです。
というわけでここからは、新しい『Z』の機材を使ってみて気付いた点を書いていきます。
間違いもあるかもしれませんが、気付いたら教えて下さいね!
それではいきます。
いきなりまとめ
最初に2ヶ月使ってみた結論を言ったほうが良いでしょう。
結論を一言で言うなら、「代え難い魅力もあるけど、強烈なインパクトはなく、改善点は多々ある」といったところでしょうか。厳し目に言うと。
D700からD800Eに替えたときほどの感動はないです。
あのときはセンサーの進化が凄かったんです。
また値段が高額なことを考えるとコスパはやや微妙で、”どうしても”という点がなければ中古のレフ機を買った方が圧倒的にコスパは良さそう。
製品ライナップの現状から言うとレンズは素晴らしいがボディはまだまだという世間の声が非常に正しい気がしています。
現在まだD800Eを1台は手元に残していますが、すぐにこれを処分することはないでしょう。
確かに良い点はあるものの、レフ機のほうが良い点もいくつかあり、ある意味当然ながら、「完全に代替される」ということにはならないと思われます。
ここからは項目ごとに詳しく掘り下げていきます。
乗り換えを検討している人の参考になれば幸いです。
軽量コンパクトボディ
ボディはめちゃくちゃ軽くて小さくなりました。やはりこれぞミラーレス。
フルサイズカメラなのにオモチャのようなサイズ感です。ミラー機構が無いことでメチャ薄くなりました。
それでいてグリップ部分はしっかりしているので片手で持っても割と安心です。心配していましたがホールド感は大丈夫。
軽量化の恩恵としては、持ち運びがラクというところですが、それは色々な運搬に関わってきます。
ザックに入れて登山する場合などが最も恩恵がありそうですが、それ以外にも手に持ったまま歩く場合や、三脚に固定したまま持ち運ぶ場合などにも軽いほうが助かります。
三脚に固定時は、雲台の締め付けが弱くて動いてしまうようなことも少なくなるし、持ち運びや操作で疲れにくいということは、より丁寧な取り扱いや、丁寧な撮影に繋がります。
「体力温存」は意外と重要な写真撮影のテーマです。
コンパクト化のデメリットはあまりないのですが、強いて言えば薄くてレンズ交換が少しだけしづらい感覚があります。
あとは前後に幅のある大型の雲台においては、ボディが薄すぎるためレンズが雲台に干渉してしまいます。
定番のハスキー雲台でZ24-70を装着するとかなりギリギリの状態に。
あとは後述しますが、各ボタンが小さくなったため、手が大きめの人は操作しづらいかなという印象です。
ボタン配置は改善の余地あり
ボディのコンパクト化に伴い、ボタンがかなり小さくなり狭い箇所に密集するようになりました。セレクター+OKボタンの部分がかなり小さく、「OKボタン」は爪で押すような感覚に近いです。
まだ余白はあるのでもう少し大きくして欲しいところ。
手の小さい女性くらいでちょうどいいサイズ感に思えます。
男性の手だと、かなり繊細な操作が必要。
また、D800系と比べると、P/M/A/S等のモード変更がダイヤル式に変わり、左手での操作になります。
右手だけでモード変更ができなくなってしまいました。
その分、右手だけで拡大・縮小やメニュー表示ができるようになりましたが、好みがあるでしょうね。
レフ機の「ボタンを押しながらダイヤルを回す」タイプの操作は、一見分かりづらいものの実はかなり使いやすくて良かったのですが。
ボタンについては2つのファンクションキーを含め、色々とカスタムできるので自分好みにカスタマイズすると便利になると思います。
ただ、割り当てられない機能があったり、メニューを呼び出した後に選択する動作が必要だったりと、全てを思い通りにすることはできず妙にストレスが溜まります。
操作の手数を極限まで少なくするのが良いデザインだと思います。
またかなり個人的な感想ですが、シャッターの近くにあるISOボタンと露出補正ボタンを間違えやすく、また露出補正ボタンは良く使う割には押さえにくい位置にあるように思えます。
その割に、画面表示を切り替えるDISPボタンが妙に離れていて押しづらいです。
基本的には悪くないとは思いますが、まだ改善の余地はありそうです。
そしてボタンイルミネーション(ボタンが光る)はなしです。
D850に搭載されている機能です。
指で覚えてしまえばいいのですが、せっかくなら光って分かりやすい方が良いですよね。
バッテリーの問題があるのかもしれません。
レンズは意外とデカい
Fマウント大三元とZマウント大三元での比較になりますが。
標準域のZ24-70/2.8は少し軽く、小さくなりましたが、驚くほど小さいわけではありません。
また既存の機材が旧型の24-70だったので、フィルター径が77mm→82mmにアップしました。
既存システムではレンズキャップやフィルターも共通で使い回せて便利でしたが、まあここは我慢しよう。
望遠域のZ70-200/2.8は、正直言ってあまりFマウントとサイズが変わりません。
こちらもFマウントでは旧型のVR IIを使っていました。
重さはいくらか軽くなっているようですが、大きさはほぼ変わらずコンパクト化にならずです。
ただ描写は素晴らしい!(後述)
広角域のZ14-24はまだZマウント版は手にしていませんが、知人のものを触らせてもらったところ、神レンズと言われていたFマウント版よりかなり小型軽量化していました。
大口径マウントは広角レンズには恩恵が大きいようですね。
ベース感度ISO64
最初は気付いていなかったのですが、Z7のベース感度はISO64。(公式な仕様ではベース感度という言葉は使われないですが。)
ベース感度が低いと使い勝手は悪いですが、ダイナミックレンジが広くなる等、低感度での画質に恩恵があるようです。
ニコンD700のベース感度は200。D800Eは100でした。
D810から64を採用しているとのこと。
Z6はベース感度100なので羨ましい。
D800EではISO100と200でほとんど画質に差がないように感じられ、ISO200をほぼ常用していました。
それが今回ベース感度が64となり、ISO200を使うと少しノイジーな感じ。
細かくみればある程度ノイズ感が見て取れます。
今までは気軽にISO200でしたが、Z7では可能な限り感度を下げて撮るようになりました。
高画素化の影響が明らかにありそうで、あとはノイズ処理の程度や鑑賞サイズを合わせた場合に厳密にどう違うかも検証したいですね。
もしかすると同じ条件に揃えると大差がないかもしれません。
手持ちの場合は感度を下げるとブレやすくなりますが、それに関しては手ブレ補正が打ち消してくれそうです。
高感度性能は変わらずか
厳密な検証をしていないので感覚値ですが、話に聞く通り高感度性能はD800Eからほとんど変わらない印象です。
少し改善しているのかもしれませんが、気付かないレベルです。
センサーの高感度性能は、D800シリーズが登場してからほぼ頭打ちに近い状態です。
ソニーのカメラはセンサー性能が頭一つ抜けているとのことで、羨ましく見ています。
技術の進歩で最も期待している分野がこれです。
星空を撮りやすくなる日が来るのを期待しています。
センサーは進化していないのか
ニコンD800/D800Eは衝撃的な印象を残したカメラで、明らかにセンサー性能が伸びました。
実際に使っていたD700と比べても、圧倒的に高画素化した上に、さらにダイナミックレンジや高感度にも強くなっていました。
しかしそれから約9年が経っても、センサー性能の根本的な底上げはないように感じます。
これが、私が長らくカメラを買い換えなかった理由です。
そして今回も噂通り、センサー自体の大きな進化を感じることはありませんでした。
感覚値では、D800Eと比べて、ダイナミックレンジは同等程度、高感度性能も同等程度という感じでしょうか。
場合によっては高画素化の影響で低下しているように感じることも。
裏面照射型CMOSセンサーというのも、違いが表に出てきていません。
もうカメラのセンサー技術は頭打ちなのでしょうか。
やはりZレンズの素晴らしさがあるので、センサーが進化した未来に大いに期待したいです。
Zレンズの素晴らしい描写力に拍手
こちらが最大の魅力になるとは思っています。おそらくニコンさんが命を懸けている部分のはずです。
解像感は実に見事です。絞り開放のF2.8から隅まで十分満足できそうな解像度を誇ります。
どのレンズでも、45MPの高画素化の上で等倍比較しても36MPの旧システムに勝る解像感だと思います。
全体的に1~2段階くらい解像度が鮮明になった感覚があります。
とくにZ70-200/2.8のほうは圧倒的で完璧に感じられました。
少しデカくて重たい以外は申し分のないレンズではないでしょうか。
ここまで完璧なレンズならお高いお値段も納得するしかないかもしれません。
一方でZ24-70/2.8のほうは少しだけ描写が気になります。
基本的には素晴らしい描写ですが、点光源があまり綺麗に描写されない印象です。
F4くらいまでではコマフレアが目立ち像が乱れている印象。
また遠景の木々等は精細に描写しているように見えるものの、富士山の山肌などを見るとやや荒い感じに見えます。
描写の甘さが被写体によって表れてくるような印象。
周辺光量落ちも大きいので星景撮影には向かないかもしれません。
少し評判より悪い印象で、ひょっとするとハズレ個体を引いてしまったのか?と思っています。
なんとなく感覚的には、調整すれば本来はもっと良いレンズなんじゃないかと思ってしまうのですが。
さすがに同じレンズを何本も買って比べるわけにもいかず、今のところ「そういうものか」と飲み込むしかありません。
前評判からするとやや期待外れであるものの、ズームレンズとしては十分すぎる解像度を持っているとは思います。
巷では「Zレンズに外れ無し」というフレーズが出るほどなので、可能ならレフ機でこれらのレンズを使いたいくらいです(構造上、無理)。
手ブレ補正が超強力
Zシリーズになってボディに手ブレ補正機構が入りました。
さらにレンズにも手ブレ補正機構が追加で入っているものがあります。
これが使用してみてかなり強力な印象で、「200mm,F8,PLフィルター使用」等の条件でもほとんどブレなく撮影できるため望遠でも三脚が要らなくなりました。
望遠のZ70-200では、レンズの手ブレ補正+ボディの手ブレ補正が働き、スペック上5.5段分の効果とされています。
Fマウント旧型70-200(手ブレ補正3.5段)はFマウント新型70-200(手ブレ補正4段)よりも効果が低く、さすがにPLフィルターを使うとブレ量産でした。
Zは実際に使用した感覚でも明らかに効き目が段違いに良いです。
望遠でも手持ちでバシバシ撮れるという力を手にして、機動力がより高まりました。
また標準・広角でも絞り込んで手持ち撮影がしやすくなったので恩恵が大きいです。
元々PLフィルター(明るいもの)+手持ちでも最大F13程度で撮っていましたが、さらに絞り込んでの撮影も手持ちで可能になりそうです。
標準のZ24-70のほうはレンズ自体に手ブレ補正が非搭載であるため、ボディのみの動作のよう。
Z70-200ほどの補正効果は確かにないですが、無補正よりは良いです。
Zボディ+Z24-70の場合はボディのみで5段ということでしょうか。
(Fマウントの新型24-70は私は使っていませんが公称4段。)
風景は三脚で撮影するイメージが強いかもしれませんが、手持ちで自由度を高めるのも非常にオススメです。
ここは素晴らしい進化ですね。
三脚が不要になると、天気を見ながら車で移動する場合などに機動力が上がるというメリットもあります。
気になっているのは、キヤノンのEOS R5/R6では手ブレ補正対応レンズとの組み合わせで最大「8段」の手ブレ補正効果があるとして2020年に発売されています。
あまりニコンから鞍替えする人はいませんが、十分魅力のあるシステムだと思って見ています。
AF難あり、ピントをよく外す
はい、これは致命的な問題です。
事前レビューでこのような話は聞かなかったのですが、ピントを外す確率がかなり高いように思えます(体感値)。
AF速度は非常に速くノンストレスです。
Z7のAFは「像面位相差AF」と「コントラストAF」を組み合わせた「ハイブリッドAF」とのこと。
コントラストAFなら精度も高いと思ったのですが、なぜか良く外します。
合う時はピタリと来るので調整は必要ないですが、一方で合焦のサインが出ても少しズレていることが頻繁にありました。
(状況にもよるし感覚値ですが数十回に1回くらい?)
レフ機のときはこのような微ズレは特に明るいシーンではほとんどなかったはずです。そもそもAFの仕組みが違うので、特性は違って当然ですが。
都度確認しないと不安なので、AF使用時でも拡大表示して目視で合焦を確認してからシャッターを切るような撮り方になりました。
「1枚ずつじっくりしっかり撮る」というスタンスで構えればそれもアリかと思いますが、プロが使う機械としては失格のような気がしますね…。
当然ながら被写体によって精度が異なると思います。
被写体は全て遠景の富士山なので、遠くの被写体が苦手なのかなと思っています。
空気が霞んでいたり揺らいでいると、映像からピント位置を正確に見つけるのは目視でも難しい場合もありますので。
極端な逆光・遠すぎる被写体・コントラストが薄いものなどは苦手なように思えます。
レンズはZ24-70、Z70-200どちらでも確認。またPLフィルター使用時のほうが外す確率が高いという感覚値です。
またオススメの設定として、ファンクションキーに「拡大画面との切り替え」を設定すると拡大/復帰が素早くできますので、シャッターを切る前にきちんとピントが来ているを確認するのは容易です。
そもそも、レフ機ではピント確認するためには一度撮影するか、「ライブビュー」モードに入ってから拡大する必要がありましたが、
ミラーレス機では常に電子映像が出ていますので撮影前の確認作業が飛躍的に簡単になったのは大きな恩恵でしょう。
そう思うと「きちんと確認してから撮る」スタイルも受け入れやすいかと思います。
暗所でのAF性能
ローライトAFの存在を後から知ったので追記・修正しました。
通常AFではレフ機よりも性能が落ちたように思えましたが、新しく「ローライトAF」という機能が登場しました。
これを設定でONにしておくと、通常AFよりスピードが落ちるものの、暗い状況でもAFが使える場合があります。
ローライトAFを使った場合はD800EよりもAF性能が上がっています。
ただ被写体や微妙な明るさの違いでかなり検出性能が違うので、万能というわけではありません。
ピントをうまく検出できないと、数秒~10秒くらい迷ったりもしますので、逆にストレスとなる場合も…。
ローライトAFを使用時も、やはりちゃんと合焦していない場合があるので、ミスしたくない場合は拡大表示での確認が必要でしょう。
また、夜景などの点光源でのAFについては、D800Eではかなり信頼度が低く使わないほうが良かったのですが、
Z7では、外すケースもあるものの、合ったときはかなり精度が高く、実用性が高いと思いました。
きちんと確認していれば、夜景などの点光源でのAFも使えそうな感じです。
まだあまり多くのシチュエーションで試せていないので、引き続き様子を見たいと思います。
ファインダー像は違和感なし
私としてはパナソニックのミラーレスを使っていたときに経験済みのEVF(電子ファインダー)。
あの時から特別な不便は感じていませんでしたが、今回のニコンミラーレスも違和感なしです。
光学ファインダーと電子ファインダーはそもそも根本から仕組みが違うわけで、この「違和感がない」というのは素晴らしいことなのかもしれません。
光学ファインダーのほうが見ていて気持ちが良いのは事実です。
一方で電子ファインダーのほうが撮影後の画像に限りなく近いものを見られるので、結果に拘る場合にはEVFのほうが適しているとも言えます。
ただ、電子映像なので少し目が疲れる印象があります。
電源を入れないと見えないファインダー
これはミラーレスカメラの構造上、当たり前中の当たり前なのですが、少しだけ不便に感じます。
電源を入れてから立ち上がるまでにややタイムラグがありますし、待機状態になっている場合もボタン等を押して復旧させなければなりません。
また長時間露光をして「長秒時ノイズ低減」を実行中もファインダー確認ができないため、処理中に次のカットの構図を決めるということもできません。
まあこれは機械の構造上仕方ないので、素直に諦めるしかないと思っています。
ファインダー内で画像確認できる
撮影した画像を確認することもできますし、撮影後の仕上がりを確認しながら構図を取ることもできます。
「Lvに撮影設定を反映」という項目があるのでONにしておくと、設定のミスが減るでしょう。
レフ機では光学ファインダーなので、どうしても肉眼でのイメージ通りに画像が出てこないケースがあります(とくにハイコントラスト・逆光などの場合)。
電子ファインダーではそういったギャップがかなり減るので、ミスの少ない撮影をするには良い機械だと思います。
暗闇でのファインダー性能
暗所でも明るく見る方法が分かったので追記・修正しました。
噂では暗所でも見やすくて良いと聞いていたのですが、使ってみたところ、そうでもない。
ファインダーを覗いた時、肉眼より良く見えるか否かがひとつのポイントだとは思います。
(EVFなので背面モニターも同様です。)
結論から言うと、普通に使っていると暗所には弱いが、「プレビュー」によって明るくすることができます。
Z7では、普通に使っていると、暗いところで星空などを撮りたい場合に、肉眼よりも見えないので構図が取れません。
D800Eの光学ファインダーでは、F2.8のレンズを付けていれば普通に肉眼と同等に見えました。
夜でも富士山がどこにあるかは分かります。
明るくするための設定も見当たらず困っていましたが、「プレビュー」ボタンを使うことで画面が明るくなることが分かりました。
絞りを開け、ISO感度を上げる等して、明るく撮れる設定にする必要がありそうです。
その状態でFnキーなどに割り当てた「プレビュー」ボタンを押すと、押している間はファインダー/モニターが明るく表示されます。
ファインダー像が暗くて困るケースはあるはずなので、もう少し分かりやすい方式を導入して欲しいですね。
ミラーレスカメラの特性上、プレビューの必要性をあまり感じなかったので最初はファンクションキーから外していましたが、必要なので戻しました。
それでも肉眼よりはやや見づらい印象で、画面はかなりノイズがうるさくなるため綺麗な映像ではありません。
光学ファインダーの方が見やすいのは間違いないです。
Z6のほうが感度が1段ほど高い仕様なので、Z7よりもよく見えるかもしれません。
なおソニーのミラーレスでは「ブライトモニタリング」という機能があり肉眼以上に見えるそうです。
ソニーのカメラはそもそもセンサー自体が高感度に強いと言われていますが、ニコンにも分かりやすい設定を導入して欲しいですね。
急激な明るさの変化には弱い
具体的には、レンズキャップを外した場合です。
電源ONの状態でレンズキャップをしていて、そこからキャップを外すと露出が急激に変わるため、明るさが調整されます。
これが2~3秒くらい掛かるので、かなり待たなくてはいけません。
(ファインダーも背面液晶も同様。)
先にレンズキャップを外した状態で電源をONにすると問題ないので、後から外す場合のみ余計に待たされる事になります。
光学ファインダーのない、ミラーレスならではの問題です。
太陽光などでセンサー焼けしないようキャップをすることもあると思うので、制御でうまいことやって欲しいです。
タッチパネルは微妙
タッチパネル操作には期待していましたが、微妙な仕上がりだと思います。
レフ機のD800EやD810は非対応で、D850からは対応していました。
特に残念だったのは①タッチによる画面の拡大ができないこと、②タッチでシャッターを切るとAFが動いてしまうことですね。
①ついて、タッチでAFのみを動かすことはできるので、それによりフォーカスポイントを選択後、手動で拡大表示にすることはできます。
しかし無駄にAFが駆動してしまいスマートではなく、暗い状況などで合焦しなかった時に元々のピントからズレてしまうこともあります。
ピントを「合わせるため」ではなくピントを「確認するため」に位置を選択したいのです。
結局、確認したい場合はセレクターでせっせと位置合わせをしています。
②ついては、AFを切ればタッチでシャッターのみになるのですが、
やりたいことは「親指AFでピント合わせ後、画面タッチでシャッター」なので、いちいちAF/MFのり着替えが必要では面倒です。
画面タッチでシャッターを切りたい理由は、ブレ防止が主な理由なので、レリーズを使うなりディレイを使うなりで対応しています。
タッチでシャッターのみができれば、3つ目のブレ防止の選択肢になります。
一方、画像を確認する場合はGoodです。
画像再生ではダブルタップで任意の場所を拡大表示できるので、ピントやブレの確認が素早くできます。ナイス!
その際、画面の下の方をタッチするとスクロールバーのような物が出てきて邪魔になります。これは個人的には要らないです。
二本指で拡大したり、スワイプすることもできますが、iPhoneのようなスムーズな動きを期待してはいけません。カクカクです。
操作にタイムラグもあります。
しかしスマホの画面とは方式が違うため、手袋をしていても操作できます!
サイレント撮影の恩恵
シャッターに関連していくつかポイントがあるため1つずつ解説します。
1つは『サイレント撮影』。
”サイレント”という名前なので「音が出ない」ことが押し出されたネーミングになっていて、AFの合焦音が消えたりもするのですが、その本質はそもそものシャッター機構の動作の違いです。
電子シャッターとなり物理的にシャッター幕が動かないため、①まったく振動がなくブレない、②太陽などの光源がシャッターに反射しないという恩恵があります。
なお、風景撮影では「ローリングシャッター歪み」はほとんど気にならないと思いますが、「長秒時ノイズ低減」が利かなくなることには注意です。
また室内撮影では照明のフリッカーが縞模様で写るケースがあります。
なおD800Eでは電子シャッター機能はなし、D810では「電子先幕シャッター」が搭載、D850で「電子シャッター(先幕も後幕も電子)」が搭載となったようです。
昔からあっても良さそうな機能だとは思いますが、ようやくこの機能を手にしました。
とにかく、望遠撮影でシャッターブレを気にしなくて良いのが有り難い。
あとは純粋に、静かに撮影できるのも良いと言えば良いです。
本当に全く音がしないので、自分でも撮っている感じはないし、隣で誰かが撮影していても全く無音ということで少し不気味です。
一眼レフの独特のシャッターを切る楽しさは、無くなっていきますね。
一眼レフではミラー動作(ここが一番音が出る)+シャッター動作の音がありました。
今回のZ7ではミラーはそもそも無く、シャッターの動作も無くすことが可能ということです。
また、個人的に重要だったのが、②の太陽を撮影したときに上下に出るフレアーのような反射が出なくなるということです。
これは絞りがF10以下くらいのとき、とくに絞りを開けたときに目立つのですが、太陽が上下に光を反射して滲む現象があるのです。
これはミラーやシャッターを上げた状態では写らないので、レンズのゴーストやフレアーではないことは分かっていました。
ミラーアップをしても発生するので、ミラーのせいでもないことが分かっていました。
その正体はどうやらシャッター幕の反射だったようで、今回、初めてサイレント撮影によりシャッター幕が動かない撮影をしてみて、その反射が消えることが確認できたのです。
このお陰で絞り開放などで太陽を撮ってもうるさい反射がなく、綺麗な描写になりました。これは大きいです。
サイレント撮影は素晴らしい。
シャッターのディレイでレリーズ要らず
【訂正】D800Eにも搭載されていましたが、使用したことがありませんでした。
D800/D800EやD810では1~3秒、D850やZ7では0.2~3秒の間で、シャッターを押してから撮影までのタイムラグを出してくれる機能です。
これにより、三脚撮影時のブレを抑えることができます。
これまではレリーズを使って、カメラに触れないようにして撮影するのが当然でした。
三脚を立てたらレリーズも用意して接続するのが基本。
Z7を購入後、端子がD800系とは異なるため、レリーズも購入しました(いつも互換品ですが)。
D800系の丸形の10ピンターミナルはボディの正面に接続口があり、しかも接続方向に対してケーブルが直角に出ているので、収まりがスマートだし引っ張っても外れたり折れたりする心配がありませんでした。
一方で10ピンではない端子(名前ある?)は接続方向にまっすぐコードが伸びる形状で、昔D7000を使っているときに横に引っ張って壊したこともあった。
またボディの横に飛び出す形になるので非常に収まりが悪い。
そういうわけでレリーズケーブル周りでも不満を持っていたのですが、ディレー機能があることに気付いてからは、レリーズを差すことがほとんどなくなりました。
基本的には三脚撮影時は「1秒」のディレーを設定することで、指でシャッターを押してもブレる心配はありません。
これまではセルフタイマーの2秒を使うこともありましたが、補助光が光ったり音が出たりと弊害があり、また2秒は少し長すぎます。
ディレー機能はおそらくブレの為にある機能で、需要に合致しました。
また、秒数を細かく設定できるのもGoodです。
不安なら3秒ディレイとすれば三脚のブレはほぼ確実に落ち着くでしょう。
それでもなお不安だったり、確実に三脚を動かしたくない場合にのみ、レリーズを接続すれば良いのです。
レリーズの準備と抜き差しが不要になったことで、カメラのセッティング・撤収が素早くなったということはかなり大きいです。
無駄なことに手間を掛けたくない。基本的にかなり面倒くさがりな性格なんですね。
ただ1秒ディレイすればタイムラグが1秒あるので、シャッターチャンスを逃す恐れもあり、本気で集中して撮影したい場合、レスポンスが求められる場合などは、やはりレリーズが必要となります。
背面モニターのチルト
これは、ないよりは良いですがさほど大きなインパクトはない印象でしょうか。
レフ機のD850には搭載されています。
「バリアングル」式ではなく「チルト」式と言うようです。チルトは自撮りはできません。
画面の角度を変えられるようになったため、極端なハイアングルやローアングルで映像を確認しながら撮影できるようになります。
ハイアングルが必要なら脚立に乗り、ローアングルが必要なら地面に這いつくばれば良いので、どうしても必要な機能とは言えない気がしますが、あれば便利です。
実際に、脚立などを持っていない状況で、ハイアングルが撮りたくなれば、両手を目一杯上に伸ばして撮影する、などということができます。
準備なしでも気軽にハイアングル・ローアングルが試せるので、新しい構図や撮り方が生まれる可能性がありますね。
前景を入れての撮影の場合、「脚立を出すのは面倒だけど、少し上のアングルから撮りたいとい」うことはけっこうあります。
高速なXQDカード
Z7ではメモリーカードとしてXQDカードが採用されています。
2012年のNikon D4から採用されている比較的新しいメディアです。
これまではコンパクトフラッシュ(CFカード)を使っていたので、メディアも新たに必要となります。
メディアとしては高額な印象で、中古品で2枚と、カードリーダーも合わせて購入しました。
大きさはSDカードよりも少し大きく、厚みがSDカードの2倍くらいで、絶妙なサイズ感のメディアです。
私は動画撮影や連写はしないので、撮影時はとくに何も感じませんが、PCにデータを取り込むときに驚きました。
仕様上、CFカードの3~4倍くらいのスピードがあるようなのですが、取り込みが非常に早かったです。
画素数も増えてデータサイズは巨大化していますが、スピーディに取り込みできました。ここはストレスがかなり減りましたね!
なおシングルスロットを採用したことでユーザーからの不満が続出し、後継のZ6IIやZ7IIではSDカードとのXQDのダブルスロットが採用となりました。
個人的にはこれまでもメディア1枚しか使用していなかったので、シングルスロットで問題ありません。(XQDカードを家に忘れたらアウトかも!)
バッテリーの持ちは
ミラーレス機と言えば、気になるのがバッテリーの持ちです。
ファインダーや液晶に映像を映すために、常にセンサーから光を取り込んでいる状態です。
レビューや噂を聞く限りでは、ニコンさんは控えめに見積もって数値を出しているが、「実際はかなり撮れる」という感じでした。
実際に使ってみてどうだったかと言うと、確かにそれなりには撮れると思います。
ただ、レフ機と比べてしまうと、やはり消耗が早いですね。
個人的には、レフ機での「昼間ならほぼ無尽蔵に撮れるぜ」というあの感じは好きだったので、少し残念です。
予備バッテリーは常に持ち歩く必要があると思います。
最近は長期間の撮影の旅はあまりしませんが、しばらく充電できない環境の場合は不安かもしれません。
なお、操作しないと30秒で待機状態に入るのがデフォルトだったと思いますが、20秒にして電力消費を抑えるようにしています。
(再起動時に電力食うってことはないよね?)
バッテリーは共通だった
Z7になり、レフ機とはバッテリーが変わるものだと思っていたが、実は互換性があり共用で使えることが分かりました。
D800Eのバッテリーは「EN-EL15」、Z7のバッテリーは「EN-EL15b」。
なおD810はD800Eと同じ、D850は「EN-EL15a」または「EN-EL15b」、Z7IIは「EN-EL15c」とのこと。ややこしいですね。
見た目の色や型番は違うバッテリーですが、形は同じで、以前のレフ機のバッテリーも使用可能。
最大で5~6個くらいの予備バッテリーを持っていたので、これは助かります。
ただ、新バッテリーの方が持ちが良いとらしいので、もし旧バッテリーの持ちに不満を感じたら、最新のバッテリーを予備でも買い揃えたほうが良さそうです。
2ヶ月使ってみて、確かに新バッテリーのほうが持つような気はしますが、2倍とか大きな差はないような感覚です。
大きく見積もって1.5倍くらいの差でしょうか。
あとは気になるのは、バッテリーチャージャー(充電器)のコードが付属していないのでコンセントに直接差すタイプになっていること。
形状として使いづらい感じです。
4種類のバッテリーの違い
ニコンの4種類(無印,a,b,c)もあるバッテリーについて違いを調べてみましたが、公式な情報は少なかったです。無印~bまでは同じ容量1900mAhで、cのみ2280mAhに容量アップしているようです。
無印~bまでは同じ容量にも関わらず、Z7で無印やaを使うと、bよりも減りが早いと公式に書いてあります。
またbについては、調べると色が黒いものとグレーのものがあり、私のZ7に付属していたのはグレーでした。混乱します。
基本的に全てのバッテリーやチャージャーは相互に互換性があると考えて良さそうですが、カメラ本体を接続しての充電は成約があるようです。
(私はバッテリーを外して個別でしか充電しないので問題なし。)
色作り(画作り)の変化
ここもカメラの核心部であり、重要なポイントです。
実はニコンはD800/D800Eの後から色作りを変えたという話は知っていました。
知人からももD810、D850では赤色の発色が綺麗に出ないと聞いていました。
赤や黄色が強い傾向から、緑や青の発色が良くなったとの話でした。
今回、確かにその傾向が感じられた気がします。
同じ被写体で正確に比べたわけではないのですのが、何度も撮影を重ねる上でその印象は確かにありました。
朝焼けに染まる富士山の「紅富士」の色があまり綺麗に出ないなと。
肉眼で見る「赤の鮮やかさ」がちっともカメラに反映されなくてガッカリもしました。
iPhoneのほうが綺麗に撮れているんじゃないかと。
今回のシステム変更では、現像に使うソフトもLightroom 4からLightroom Classicに変更しているので、その影響も多少あるかもしれません。
微妙な色味の違いは、現像時に調整することで補えるとも言えるかもしれませんが、今のところ、現像時に調整しても少し違和感を感じています。
しかしまだ「気のせいかもしれない」という領域を脱していません。
同じ被写体をじっくり撮り比べて、厳密に比較しないと答えは出ないかもしれません。
「現像で何とでもなる」問題なのか、「根本的に色がうまく出ない」なのか、じっくり考察する必要がありそうです。
もし後者であれば、根本から考え直さなければいけない事になります。
なお色以外の部分(コントラスト等)においても、なんとなく違いを感じますが、まだ言葉で表現できるほど掴めてはいません。
レンズもボディも違うので差はあるはずですが、大きな差ではないと感じています。
D700からD800Eにしたときは大きく変わりました。
ヴィネット(周辺光量落ち)とその補正に手を焼くことに
少しマニアックな内容になってきます。
周辺光量落ちが激しいと補正するのが難しくなります。
Z24-70は開放のF2.8で、Fマウントの24-70よりも激しく周辺光量が落ちます。
開放で使った場合はかなりキツイ暗さになります。
そしてそれ以上に問題なのが現像ソフトのLightroomで十分な補正ができないこと。
私の環境(Lightroom Classic)でですが、Zレンズのプロファイルは適応できず「内臓プロファイル」を使うしかなくなっています。
しかしこの内臓プロファイルを適応してもヴィネットが完全に補正はされません。
また、撮影時の設定を反映しているようなので、撮影時に補正を「強め」に設定すべき状態となっています。
(周辺光量をあえて落としたい場合はレンズの描写に頼るのではなく後補正するほうが融通が利くと考えています。)
Fマウントシステムの場合はいったん完全にフラットにすることができたので後の調整が自在でした。
Zマウントシステムでは実質的に、開放付近で撮影すると調整しづらくなるため、絞る必要が出てきてしまっています。これは勿体ない。
LightroomさんはなぜZレンズのプロファイルに対応しないのでしょうか。
詳しい方がおりましたら教えて下さい。
またニコン純製ソフトのCapture NX-Dを使っても完全にスムーズに補正はできず、ヴィネットの扱いが厄介になっています。
Z24-70の光量の落ち方の酷さもあり、ちょっと開放付近では扱いづらいなという印象です。
一方、Z70-200のほうは調子が良いです。
Fマウントに比べて絞り込まなくても周辺光量の落ち方が穏やかで目立ちにくく感じます。
Fマウント70-200では、F8~F11あたりでもまだ周辺光量落ちが気になるため基本的にF13まで絞って使用していましたが、
Zマウント70-200になるとF8でもかなりフラットな画像が得られるため、撮影がだいぶ楽になりました。
シャッタースピードの面でも、解像度の面でも、センサーゴミの面でも救われます。
「基本F13で撮る」というのはなかなかの重荷でしたからね。
ヴィネットの問題は意外と地味ではありますが、仕上がりを左右する大事なポイントだと思っています。
そういえばセンサーが小さいカメラだとあまり悩みがなかった気がします。大口径で問題になりやすいようです。
ヴィネットに限らず、RAWで撮影した画像については、撮影後にパラメータを変更できるのがこれまでの基本的な考えでしたが、
内蔵プロファイルの使用によって、撮影時に設定した設定が後では調整できないことになり、常識が変わりました。
まだ細かい仕様などは分析できていません。
逆光(太陽を入れて)での撮影
カメラメーカーはあまり考えてないような気がしますが、風景カメラマンとしては重要なポイントとなる部分です。
まずZレンズの仕様として基本的に絞り羽9枚で、最近のレンズはほとんど奇数絞りになっているのが残念でなりません。
ボケを綺麗にするためのようですが、パンフォーカス風景がメインで太陽や夜景を撮る場合には偶数絞りの需要はかなりあると思います。
選べるようにならないかな…。
光芒(光条)の出方は、Fマウントのレンズよりだいぶソフトになりあまりトゲトゲしていません。
ちょっとインパクトに欠ける描写で、個人的には残念です。
光芒にインパクトを出したい場合はFマウントレンズを使う選択肢も有り得そうです。
またゴーストはあまり酷くは出ず、割と控えめな印象で、Fマウントレンズより改善している印象です。
Z24-70では青い点状のゴーストがぽつっと出るのでうまく消去できないと妙に違和感が残るかもしれません。
Z70-200のほうも、比較的逆光には強いように思えますが、ゴーストは普通に出ます。
またおそらくセンサーの反射と思われる模様が、Z7ではD800Eと比べると出やすくなっているように思えました。
これはデジタルカメラの欠点なんですよね。
センサーの仕様が変わったのかもしれませんが、なんとかして上手く防ぐ方法はないのかと思ってしまいます。
センサー反射が出づらいカメラがあれば逆光専用に買っても良いくらいです。
逆光時の撮影は、太陽高度や大気の霞具合でかなり条件が異なってきますので、改めて検証していきたいと思います。
スマホとの通信とリモート撮影
正直、期待していた機能なのですがあまり使っていません。
設定が分かりづらいですが、カメラとスマートフォンを接続した上、スマホ側からの操作でRAW画像を取り込むことができます。(知人に教えて頂きました。)
まだ試していないのですが、スマホでのRAW現像にもこれから挑戦したいです。
結局今のところは、家に帰ってからPCで現像しています。
また、スマホと連動させることでリモート撮影ができます。
超ハイアングルなど、目の届かないところまでカメラを動かして撮影する場合や、三脚で固定して車の中から撮影など、色々用途はあると思います。
ただ、そこまで使う機会は多くないのが現状です。
また、モードやISO感度に成約があるなど、ソフト的な柔軟性がまだまだ悪く、普通にカメラを使うように撮影することはできません。
優先度が低い機能だったのかもしれませんが、ちょっと作り込みが甘いように思えます。
ニコンさんは技術屋であり、まだまだITには弱いのかなと感じてしまいます。
ミラーレスのセンサーゴミ問題
ミラーレスカメラは、センサーの前にミラーがなく、なぜか電源OFF時にシャッターも開いている機種がほとんどです。
キヤノンのEOS Rシリーズは電源OFF時にシャッター幕が閉まることで好評のようです。
ソニーも最近になりこの機能を追加してきましたね(なんとソフトのアップデートで!)。
レフ機に比べてミラー+シャッターの2つの壁がないので、かなりゴミは入りやすいと予想していました。
結果ですが、2ヶ月使ってみて、やはり汚れやすかったです。
レンズ交換の頻度が高かったことも影響しているので、厳密な比較はできませんが。
基本的にはやはり「レンズを極力交換しない」のが最も効果的です。残念ながら。
また絞りを絞っての撮影があらかじめ分かっているときは、事前に清掃するしかないでしょう。
この2ヶ月間、ボディ1台に対してレンズ2本を主に使って撮影していたので、レンズ交換がかなり多かったです。
個人的な考えですが、やはりボディは2台あったほうが便利です。レンズを交換する手間とリスクを極限まで減らしたいです。
2ヶ月の使用後、自分でセンサークリーニングを行いました。
クリーニングにはスワブタイプのものを使いますが、なんとD800Eに比べてセンサー面積が大きくなっていて、幅が合いませんでした。
仕様を見るとD800Eは「35.9×24.0mm」、Z7は「35.9×23.9mm」と、僅かに小さくなっているのですが、実際の平面としては大きくなっていました。
予想ですが、センサークリーニングをしやすいように、センサーがない部分にも表面素材の面積を追加したのではないかと思っています。
【追記】電源ONの状態でバッテリーを抜き差しするとシャッターが閉まった状態に固定されるとの情報を頂きました。
非公式っぽい方法なので自己責任となりますが、レンズ交換の際はこの方法は大いに使えそうです!
手ブレ補正の切り替えが手間
上述の通り、素晴らしい手ブレ補正性能を発揮してくれるのは良いのですが、Fマウントの時のようにレンズのスイッチで設定を切り替えることはできなくなりました。
手ブレ補正のON/OFFを切り替えるはメニューから切り替える必要があり、よく使う項目を登録できる「iメニュー」に手ブレ補正の項目を入れ込んだとしても、iメニュー呼び出し→手ブレ補正の項目をセレクト→設定を変更と3ステップあり、直感的でもないのでスムーズには行きません。
当然ながら三脚に乗せているのに手ブレ補正ONなどの状況ではブレてしまう可能性もあるし、三脚から手持ちに切り替えるときに素早く設定を変更できないのは、致命的です。
これはヤバイと思ったのですが、解決する方法がありました!
それが、ユーザーセッティングを使って「手持ち用の設定」と「三脚用の設定」を登録することです。
レフ機の時代はユーザーセッティングは使いませんでした。必要がなかったとも言えます。しかし今回は必須でしょう。
ユーザーセッティングに設定を登録すれば、ダイヤルをひとつ回すだけで一気にカメラの設定を変更できます。
私の場合はU1=手持ち用、U2=三脚日中用、U3=三脚夜間用という設定で登録をしました。
どこまでの設定が記憶されるかなど細かいクセがあり混乱するかもしれませんが、ユーザーセッティングを使いこなすとかなり便利になります。
残念な電子水準器
ここからはソフトウェア面での不満が続きます。
ニコンにとって初代のフルサイズミラーレスということもあり、ソフト的な使いづらさが多々出てきています。
まずは衝撃的な残念さだったのが、電子水準器。
D800Eでは、グリップしながら右手で押せるファンクションキーにファインダー内水準器表示を割り当てるられたので、ファインダーを覗きながら水平確認ができました。
ファインダーの下部に小さいゲージが出るだけなので、覗いている映像を邪魔しません。
ところがZ7の水準器は画面の中央にデカく表示することしかできず(ファインダーも液晶も共通)、被写体に被ってしまい邪魔です!
しかも表示を切り替えるためにはDISPボタンを何度も押すことになるので非常に面倒ですね。
手持ち撮影で水平と構図を同時に取りたい場合には明らかに使いづらいものとなってしましました。
小さい表示なら常に表示してあっても邪魔にならないくらいなんですけどね。
改善要望を出したいですね。
また、そもそも電子水準器の精度自体が少し怪しい印象を受けています。これは以前からのことですが。
電子水準器はそもそも信用しすぎず、参考程度に使って、現像時にきちんと補正することが大事です。
なぜ電源を切るとピント位置が変わるのか?
これは説明書にも書いてあり、仕様のようです。
電源を一度OFにすると設定したピント位置がズレてしまいます。
(調べるとレンズの特性のようで、他社カメラでも同様の現象があるようです。)
風景撮影ではほぼピントは無限遠に固定で、夜景などではマニュアルで慎重にピント合わせをしたりします。
それが電源を切ると台無しに。最初はかなりイラッとしました。
なので、基本的には撮影を少し休むときは電源を切らず、自動で待機状態に入るのを待つことが多くなりました。
バッテリー消耗が大きいので早くOFFにしたい気持ちがあるのですが、ピントのために切らずに待ちます。
一番イヤなケースは、長時間露光中に例えば三脚を蹴ってしまうなどのトラブルがあり、撮影を一時中断したいときです。
長時間露光や長秒時ノイズ低減を途中で中断するには、電源を切るしかないので、ここでピント位置がズレてしまいます。
最悪です。
かなり残念な仕様となっていますが、後継のZ7IIではピント位置を保存する設定が追加され、改善されたようです。
その他ソフト的な不満点いろいろ
ここからは細かい不安点を一気にまとめて。
ニコンさんはまだまだソフト分野は強くない印象ですね。
実際に使ってみると気になる点は続々と出てきます。
しかしソフト面の問題は、ファームウェア(ソフトウェア)アップデートで改善できるはずですし、基本的にはアイディアさえあれば実現できるものなので、今後の改善を強く期待しています。
撮影後の自動再生が気持ち悪い
私は撮影後には画像が自動で再生できる設定にして、常に撮影画像を確認しています。が、撮影のブラックアウトが終わったあと、一瞬だけリアルタイム画像がチラッと出たあと、撮影画像に切り替わります。
そのちらっと出るやつ、要らないですよね…すぐに撮影画像を出して欲しい。
どうも画像の書き込みや、画像として出力されるまでにタイムラグがあり、その間にリアルタイムの映像が表示されるようです。
ファインダーで見ていてもチカチカするので最初はかなり嫌でした。
また、「撮影直後の画像確認」を「する(画像モニター表示のみ)」にした場合に、撮影後にファインダーから目を離した場合ではモニターに再生画像が表示されません。
この動作はレフ機では一般的な動作なので、動き物を撮りながら確認するということができなくなっています。
風景メインならあまり問題ありませんが、使い方によってはかなり困るかもしれません。
構図を決めている間にパワーオフ
これも結構嫌な仕様ですね。設定の名前は「半押しタイマー」と言って混乱を招くネーミングとなっていますが、
一定期間操作をしないと待機状態になる設定です。
ミラーレスカメラは撮影していない間にもどんどん電池を食うので、一定時間が経過したらパワーオフにする機能は必要です。
ただ、ファインダー覗いてるときに切らなくてもいいじゃん!て思いませんか。
じっくり構図を決めていたり、フィルターの効き具合を調整している間に、パワーオフになってしまいます。
ファインダーの横にはセンサーが付いていて、顔を近づけると表示を切り替えるような仕様があるので、ファインダーを覗いているかどうかはカメラは知ることができます。
「何も操作していない」の判定方法を改善してほしいです。
撮影画像の再生画面が微妙
これは実際の写真を見てもらうと分かると思いますが、撮影画像を再生するときに、画面の下側に情報が被って表示されます。このため写真全体の構図が崩れてしまい、撮影画像の構図をを正しく評価できません。
ちょっと信じられない表示方式です。
メニューをカスタムすることで「画像のみ」の表示(情報なし)を追加することができるので、そちらで確認するようにしています。
このデフォルトの情報が被るスタイルは、非表示にしたいのですが、消すことはできないようです。
絞り値の状態が反映されない
ファインダー/モニターとも、反映されるの絞り値は開放からF5.6までとのこと。
それ以上絞り込んでも、実際にシャッターを切るまではF5.6の映像となります。
「Lvに撮影設定を反映」の設定をしてもダメです。
プレビューボタンを押すことで絞り込んだ表示に切り替えることができますが、
押している間だけの反映のため、拡大しての確認は不可です。
レフ機のライブビューで出来たことがなぜできないのでしょうか。
絞り込んだ上でピントを確認することができません。けっこう酷いです。
最後はちょっと愚痴の連発みたいになってしまいました…。
まとめ
さて、長々と書いてきましたが、最後にまとめたいと思います。
やはり当然ながら機材というのは買って使ってみないと分からないことが沢山あります。
ネットのレビューや知人の口コミは大変役に立ちますが、最後に判断するのは自分の感覚です。
今回の生々しいレビューが参考になれば幸いです。
・素晴らしいZレンズ群
・機能的な多くの改善(機動性・利便性アップ)
・センサーはあまり変わらず(将来に期待)
・ソフト的な数々の小さな不満がある
・いくつかのハード的な問題もある
今後も使用しながら追求していきたいと思います。
私としても今回の記事を作成しながら、改めて調べて気付いたり学んだことや、他社の機材について知れたことがあり、レビューにトライしてみて良かったです。
カメラ機材は高額でなかなか色々な物をテストするのは難しいのですが、またチャンスがあれば他のメーカーも使ってみたいですね。
また一つの機材に拘ることなく、シーンに応じて複数の基材を使い分ける必要もあるでしょう。
富士フイルムのGFX50やGFX100、キヤノンのEOS R5、ソニーのα7RIV等も一度は使ってみたい機材です。
もし機材投資の元が取れる境遇になったなら、手にしてみたいと思っています。
(注)今回の記事は、初回「写真・画像なし」でお届けしております。
後日写真と画像を追加する予定なので、更新をお待ち下さい。
最後までご覧いただきありがとうございました。
(記事を書くのに丸3日掛かりました。)
ニコンに要望を提出しよう
久々に機材を乗り替えたので、これまでと異なる点について色々と目についてしまいました。
ブログやツイッターで愚痴るのは簡単ですが、せっかく調べてまとめたので、ニコンさんに要望を出そうと思っています。
調べたところ以下のフォームが見つかりましたので、改めて内容を整理してから送信する予定です。
(愚痴るだけじゃなくて行動しましょう!人生の基本!)
https://www.nikonimgsupport.com/nij/NIJ_ask_support
技術的なものやハードウェア的な面では改善が難しいかもしれませんが、ソフトウェア的な部分はやるかやらないかというだけなので、比較的改善のハードルが低いと思っています。
とくに「ファームウェアアップデート」という方法は古くから定着しているので、これを使って使い勝手をバシバシ良くして欲しいと願います。
本気で写真を撮るからこそ、無駄な操作はしたくないし、自分好みにカスタマイズしたいのは当然です。
1秒のシャッターチャンスも逃したくないです。
他社の方が使い勝手が良かったら、ユーザーは乗り替えてしまいます。
機能や操作が不便だったら、スマホでいいやという気になってしまいます。
ニコンのカメラがより良い製品になりますように。
おわり
- スポンサードリンク -
Posted at 2021.01.20
Updated at 2021.01.24
ほかのブログ記事